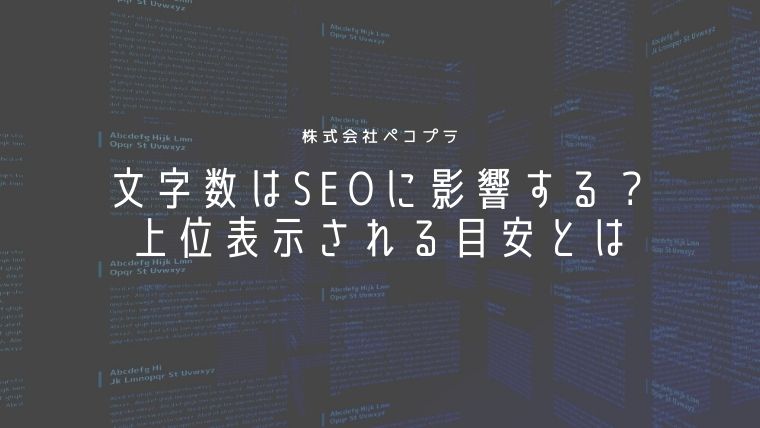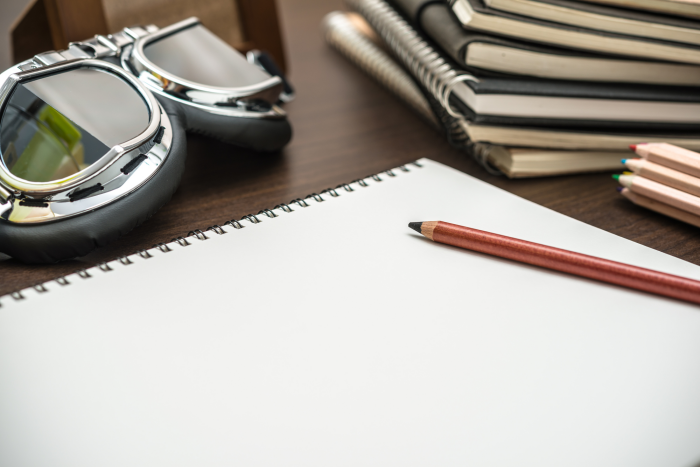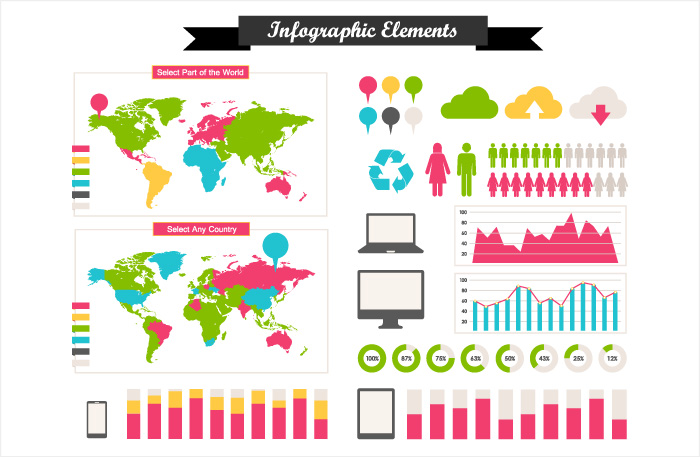文字数はSEOに影響する?上位表示される目安とは
2021.05.18
「文字数はSEOに影響するのか?」「テキスト量を増やせば検索順位が上がるのか?」という疑問は、経験値の高いサイト運営者の間でも意見が分かれているのが実情です。実際、記事の作成ルールに「〇〇文字以上」という条件が付いていることも珍しくありません。そこで本記事では、文字数とSEOの関係について解説していきます
文字数(文章量)が多いほどSEO効果が高いのか?
結論から言うと、文字数が多いからと言って必ずしも上位表示されるとは限りません。
確かに、文字数とSEOの関係は専門家の間でも意見が分かれており、「上位表示には1万文字が必須!」と主張する人もいれば、「むしろ要点だけ簡潔にまとめた1,000文字ほどが理想的!」という人もいます。
なぜ、専門家の間でも意見が一致していないのでしょうか?
その答えは、「文字数の多さ」が「ユーザーの満足度」に比例するとは限らないからです。
しかも、検索キーワードによって一言で表現すべき答えもあれば、順序立てて解説すべき答えもあり、当然ながら適切な文字数も違ってきます。
▼キーワードの性質と文字数の関係
- 2020年の新生児数:リアルな数値を記載すべきなので、少なく文字数でもOK
- SEO:仕組みや対策などを詳しく記載すべきなので、文字数も多くなる
つまり、SEOにとっては文字数よりも「いかにユーザーの質問に的確な答えを提供できているか」が上位表示の条件なのです。
Google公式見解!SEOと文字数の関係について言及
文字数(文章量)とSEOの関係について疑問に思っているサイト運営者にとって、大きなヒントとなるのがGoogleスタッフから発信されているアナウンスです。
この段落では、Googleスタッフが発信している2つの公式見解についてご紹介します。
Googleのジョン・ミュラー氏が言及!SEOと文字数は無関係
まずは、Googleのスポークスマンとして知られるジョン・ミュラー氏(John Mueller)が、2016年7月8日に開催されたWebmaster Central office-hours hangoutに参加した時のコメントを見てみましょう。
出典:English Google Webmaster Central office-hours hangout
上記のアナウンスを翻訳したうえで、注目すべきポイントをピックアップしてみました。
▼注目ポイント
- Googleは、ページ内の文字数をカウントするアルゴリズムを採用していない
- 100文字以下は低評価、500文字以上が合格といった評価基準はない
- 「ユーザーにとって有益で関連性の高いコンテンツ」をページ全体で評価している
上記のアナウンスから、Googleは文字数(文章量)が多いという理由だけで検索結果の上位に表示している訳ではない、と解釈できます。
むしろ、ユーザーにとって有益な情報を含んでいるコンテンツかどうかが重要であり、テキストや画像の量はSEOと無関係だと言い切っているのです。
文字数は品質を測る指標では無い!とミュラー氏がツイート
また、ミュラー氏は2018年7月24日に投稿したツイートでも文字数とSEOの関連性について言及しています。
https://twitter.com/JohnMu/status/1021690796691607552?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1021690796691607552&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.allegro-inc.com%2Fseo%2Ftext-contents-volume
特筆すべきは、「文字数はコンテンツの品質を測るバロメーターでは無い」と言及している点でしょう。
Googleは常々、SEOにとって最も重要なのは「コンテンツの品質」であり、ユーザーにとって役立つコンテンツこそ検索上位に表示されるべきだと言及しています。
その証拠に、ユーザーの有益性を高めるべく「ページエクスペリエンスシグナル」や「プロダクトレビュー」をSEO評価に追加すると発表しているのです。
たとえ従来の検索アルゴリズムが更新されようと新しい指標が組み込まれようと、SEOにとって「量」より「質」が重視される点は不変なのでしょう。
▼参考コンテンツ
SEO効果の高いコンテンツとは?「文字数」より「質」が重要
Googleのジョン・ミュラー氏は、上記のツイートで「少ない文字数でも上位表示されるコンテンツの特徴」について下記の2点を挙げています。
▼文字数を問わずSEOに強いコンテンツの特徴
- 検索クエリとのマッチング精度が高い
- ユーザーの知りたい情報が分かりやすく書かれている
事実、キーワードによっては1,000文字にも満たないページが常に上位表示されているケースも見受けられます。
その反面、似たような文章を何度も繰り返している内容の薄いページは、ムダに文字数だけが多いだけの低品質コンテンツだと見なされても文句は言えません。
つまり、SEOにおける優位性はコンテンツ内の「文字数」ではなく、あくまで「質」によって決定されているのです。
検索クエリについては下記の記事でも解説しています。
文字数が多いサイトが上位表示されている理由
確かに、Googleは「文字数とSEOは無関係」だと明確にアナウンスしています。
とはいえ、実際に上位表示されているWebサイトを見てみると、明らかに文章量が多い傾向にあるようです。
この段落では、なぜGoogleのアナウンスに反してテキスト量の多いWebサイトが上位表示されているのか、その理由について解説します。
文字数が多いほどSEOに有利な要素を組み込みやすくなる!
例えば、「文字数 SEO」というキーワードで検索したときに上位に表示されるサイトの文字数を調べてみると、下記のような結果になりました。
▼上位サイトの文字数
- 1位ページの文字数:約2万字
- 上位サイトの平均文字数:約5,000字
上記の結果から、やはり文字数はSEOに関係していると思われます。
これは、文字数そのものがSEOに影響しているからではなく、全体の文章量が多ければ多いほどSEOに有利になる要素を組み込みやすくなるためです。
Googleはユーザーが求める情報を提供できるサイトを上位に表示させますが、そういったサイトはコンテンツの内容が広範囲にわたるため、結果的に文字数の多いサイトが上位に表示されているのでしょう。
もちろん、たとえ文字数が少なくてもユーザーにとって有益なサイトであれば上位に表示されます。
しかし、文字数が少ないということはユーザーが求めている情報の「専門性」や「網羅性」などを満たすことが難しくなり、記事を上位表示させる難易度が必然的に高くなってしまうのです。
ユーザーニーズを満たそうとすると自然と長文になる!
SEOを考えるうえで欠かせないのが「ユーザビリティの高さ」です。
だからこそ、Googleはどれだけユーザーにとって役立つ情報が含まれているのか、コンテンツ全体の内容をSEOの評価基準として重視しているのでしょう。
実際、ユーザーが求めている情報だけでなく間接的に役立つ内容まで全てを網羅しようとすると、コンテンツの品質が向上するにつれて自然と長文になりがちです。
▼関連記事
文字数が増えるとSEO効果の高い「ユニーク単語数」も増える!
ユニーク単語数とは、ユニークワードまたはユニークキーワードとも呼ばれており、特定の単語が重複している場合に1回としてカウントした単語数を指しています。
たとえ同じ単語が10回記載されていても1回としてカウントされるため、「ユニーク単語数が多い=ユーザーにとって有益な単語の種類が豊富」と評価される可能性が高いのです。
ちなみに、検索結果の上位に表示されているWebサイトの特徴として、SEO対策の基本である「共起語」や「関連語」がタイトル・見出し・本文に数多く含まれている、という点が挙げられます。
- 共起語:コンテンツのメインKWから連想されるワード
- 関連語:特定のKWで検索した時に、予測変換で表示されるワード
特筆すべきは、ユニーク単語数が増えるほど「共起語」や「関連語」を文章に組み込みやすくなる、という二次的な効果です。
言い換えれば、文字数が増えるほど共起語や関連語を含むユニーク単語数も同時に増えるのですから、上位表示の可能性を高める効果があるのも当然かもしれません。
SEOに最適な文字数はあるのか?
Googleが文字数とSEOの関係性を否定している一方、実際には「情報量」の多いコンテンツがランキング上位を占めています。
では、SEO効果を最大限に引き出す「適切な文字数」は存在するのでしょうか?
ここからは、下記の3項目に分けて解説します。
- 本文の文字数
- タイトルの文字数
- ディスクリプションの文字数
本文SEO!最適な文字数と上位表示のコツ
残念ながら、本文に関して最適な文字数は存在しません。
なぜなら、キーワードによって適切な文字数が異なるから!強いて言えば、解説が必要なテーマで上位表示させるには、2,000~3,000文字以上が目安になります。
テーマごとの最適な文字数を割り出すには、すでに上位表示されている競合サイトの文字数をリサーチしてみましょう。
その際、文字数だけでなく見出しから内容の網羅性を手本にすると、必然的に文字数も増えてコンテンツ自体の質も向上します。
タイトルSEO!最適な文字数と上位表示のコツ
本文とは違い、タイトルには適切な文字数が存在します。
- 長くても32字以内にまとめる
- 重要なキーワードは、なるべく最初(左側)に入れる
Googleが告知していた通り、2021年3月末から全サイトを対象にMFI(モバイルファーストインデックス)の強制移行がスタートし、今後はより短いタイトルが有利になると考えられます。
スマホの小さな画面でもタイトルが見切れないよう、より少ない文字数で表現しましょう。
ちなみに、タイトルとSEOの関係性については下記の記事で詳しく解説しております。
ディスクリプションSEO!最適な文字数と上位表示のコツ
タイトルと同じく、ディスクリプション(meta-description)にも適切な文字数があります。
ただし、PCとスマホとでは検索結果に表示される文字数が異なるため、モバイルフレンドリー対策として100文字ほどにまとめているコンテンツが増えているようです。
▼検索結果に表示される文字数
ちなみに、リード文の最適な文字数はディスクリプションより少し多めの約200文字が目安です。
ディスクリプションやリード文の文字数については、下記の記事でも詳しく解説しております。
文字数を増やす時の注意点6つ
文字数を増やせば関連性の高い情報量も増加するため、結果的にSEOにポジティブな効果をもたらします。
しかし、ただ闇雲に文字数を増やしても上位表示はされません!むしろ、ペナルティを受ける可能性もあるのです。
そこでこの段落では、文字数を増やす時の注意点を6つピックアップしてみました。
文字数が多くてもコピペ・独自性のないコンテンツはNG
どんなに文字数が多くても、他のサイトから切り貼りしただけのようなオリジナリティのない文章には価値がありません。
コピペはもちろんNGですし、語尾を変えただけの文章もNGです。
オリジナリティのない文章はコピペ率が上がりやすいので、Googleからのペナルティも受けやすくなってしまいます。
インターネットでリサーチして記事を執筆することもあるでしょう。
その際は、文章を書き換えるのではなく、リサーチした内容を咀嚼し、自分の言葉で書くことを意識してください。
コピペについては下記の記事でも解説しています。
無駄な情報で文字数を増やすのは逆効果
特定のキーワードで検索した際、上位表示されている競合コンテンツがもれなく1万文字を超える長文だった、というケースもあるでしょう。
とはいえ、無理な「文字数稼ぎ」は逆効果!役に立たない情報やコンテンツのテーマと関係のない内容を盛り込んで文字数を水増しする手法は、すでに通用しなくなっています。
せっかくアクセスしてくれたユーザーを失望させるだけでなく、Googleから検索クエリとのマッチング精度が低いとみなされ兼ねません。
あくまでユーザーニーズを満たそうとする過程で文字数が増えるのなら、必然的に「共起語」のバリエーションが増加し、ひいてはKWの「網羅性」も高まるはずです。
強引に共起語を詰め込み過ぎない
多くの共起語を盛り込めば、SEOに良い影響が出やすいです。
しかし、だからといって無理やりたくさんの共起語を詰め込むのはやめましょう。
大量のキーワードを盛り込んでも文章が破綻していると自動生成のコンテンツと疑われ、ペナルティを受ける可能性があるからです。
あくまで自然な範囲に留めておきましょう。
共起語の活用方法については下記の記事で詳しく解説しています。
引用だらけの文章は避ける
引用は簡単に文字数を稼げるのでたくさん使いたくなりますが、使い過ぎはおすすめできません。
なぜなら、引用がメインとなってしまうと主従関係が逆転してしまうからです。
主従関係が逆転してしまった場合、SEOに不利に働くというよりは、引用のルールに反してしまいます。
引用をする際にはルールに従わなければ著作権の観点からアウトになってしまうので、引用のし過ぎには注意してください。
異なるテーマを混在させない
ひとつのテーマで十分な文字数を書けなかったとしても、異なるテーマを混ぜてしまうのは得策ではありません。
異なるテーマが混在してしまうと記事の専門性が下がってしまい、上位に表示されにくくなる可能性があるからです。
文字数の増やし過ぎに注意
文字数と情報量は比例するように増えて行きますが、だからと言って増やし過ぎるのも考え物です。
例えば、競合サイトが1万文字なのに対し3万文字のコンテンツを公開した場合、ユーザーから「最後まで読むのは大変そう」「まわりくどい説明は避けたい」と敬遠されるかもしれません。
箇条書きやイラストを使って、より視覚的に「分かり易さ」「伝わり易さ」をアピールした方が良いでしょう。
SEOに効果的な文字数の増やし方
それでは、上位に表示されやすい情報量の多い文章はどうすればできるのか、そのコツを見ていきましょう。
これらのコツを組み込んでいくと、自然と文字数が多くなっていきます。
ユーザーが求めている情報を漏れなく適切な文字数で書く
まず、ユーザーが検索する時の心理を考えてみましょう。
ユーザーは何かの疑問を解決するためにキーワードを打ち込み、その答えを望んでいるのです。
▼キーワードとコンテンツの関係性
- キーワード:ユーザーからの質問
- コンテンツ:ユーザーへの回答
ここで問題となるのが、キーワードからいかにユーザーの知りたがっている答えを連想できるかどうか!
ユーザーが打ち込んだキーワードから波及して「仕組みを知りたいのか」もしくは「対策を知りたいのか」と連想していきましょう。
ユーザーが潜在的に抱えている疑問に対し、もれなく回答できるのが最良のコンテンツです。
関連性の高いページへのリンクを増やす
たとえ文字数が少なくても、上位表示を狙う方法はあります。
キーワードが単純で内容の裾野が広がらない場合は、関連性の高いページへの内部リンクを増やしてみましょう。
サイトによってはスマホでの読み易さを優先するために、テーマを限界まで狭めて最小限の文字数でコンテンツを仕上げています。
その代わり、関連性の高いコンテンツにリンクを張って誘導しているのです。
▼関連記事
競合サイトの文字数を参考にする
競合サイトの文字数を参考にする手法は、ベテランライターが多用しているだけでなく初心者ブロガーにとっても手軽に真似できる効果的な方法です。
特定のキーワードで検索し、ランキング上位のページが何文字で書かれているかリサーチしてみましょう。
見出しをチェックするだけでも、情報漏れの予防につながります。
共起語・ユニーク単語を増やして網羅性を高める
網羅性を高めることで、自然と情報量が増えていきます。
網羅性を高めるとは、ユーザーが知りたいと思っている情報を汲み取り、それらを自然な範囲でできる限り多く記事に盛り込んでいくことを言います。
たとえば「SEO 文字数」と検索する人は、「文字数の多さはSEOに影響するのか?」という疑問点だけではなく、下記のような関連した情報も知りたいと考えていることが多いのです。
- どうすれば文字数を増やせるのか
- 文字数さえ増やせば順位を上げることができるのだろうか
それらを予測し、記事に組み込んでいくことで網羅性を高めていくことができます。
ユーザーの知りたい情報を予測するには、共起語やサジェストキーワードなどを利用すると良いでしょう。
共起語とは検索キーワードと共に頻出する語句のことで、共起語検索ツール等を使うことで調べることができます。
ここからは、いくつか共起語検索ツールをご紹介しましょう。
共起語検索

出典:共起語
シンプルな共起語検索ツールです。上位30位まで検索することができます。
Find word

出典:Find word
共起語が検索できるだけでなく、サイトのURLを入力することでそのサイトに足りないキーワードを教えてくれるツールです。リライトをしたいときにも便利です。
共起語分析ツール

出典:共起語分析ツール
キーワードの共起語を、「名詞」「動詞」「形容詞」に分類してサーチしてくれるツールです。SNSにて反響のあるキーワードを抽出することもできます。
サジェストキーワードは検索キーワードと共に検索されることの多い語句のことで、検索ボックスにキーワードを入力することで確認することができます。

共起語もサジェストキーワードも、あまりにも欲張ってたくさん入れすぎてしまうと、ごちゃごちゃとしたわかりづらい文章になってしまいます。上位10個くらいのキーワードは可能な限り盛り込んで、それ以下のキーワードはできれば盛り込んでいく、くらいにするとバランスがよくなります。
引用や参考を効果的に使う
引用や参考を効果的に使うことで、情報の信憑性を高めつつ文字数を増やすことができます。
引用とは元の情報をそのまま使用すること、参考とは元の情報を要約して使用することです。
ただし、引用や参考を使う場合は以下の点に注意しましょう。
▼引用や参考を使う際の注意点
- 主従関係を明確にする
- 出所を記載する
- 引用する場合はタグを使用する
- 信頼のある情報源を使用する
それぞれ、解説していきます。
主従関係を明確にする
引用や参考をする場合は、引用や参考の部分をメインにしてはいけません。たとえば、引用した文章ばかりを並べてその解説を少しだけ書く、というのはNGです。あくまでメインとなるのは、自分で書いた文章のほうです。記事の信憑性を高めるために添える、程度に考えると良いでしょう。
出所を記載する
情報源を記載するようにしましょう。WEBサイトからであれば「サイト名、URL」を記載し、引用または参考にした日付を記載するとよいでしょう。本であれば、「著者名、出版年、タイトル(巻数があれば巻数も)、ページ数」を記載しましょう。
引用する場合はタグを使用する
引用する場合は、タグを使用しましょう。タグなしで引用してしまうと、盗用を疑われる可能性があります。
例として、実際に引用してみます。たとえば、文字数について論述するのであれば、このようにGoogleから提供されている『良質なサイトを作るためのアドバイス』の一部を引用するとより信憑性の高い記事ができるでしょう。
記事が雑誌、百科事典、書籍で読めるようなクオリティか?
・記事が短い、内容が薄い、または役立つ具体的な内容がない、といったものではないか?
引用元:GoogleWEBマスター向け公式ブログ『良質なサイトを作るためのアドバイス』
引用をすると、このようになります。どこからどこまでが引用なのかをはっきりさせることがポイントです。
WordPressやブログサービスのほとんどは、ワンクリックで引用ができるようになっています。引用文を範囲指定し、引用ボタンを押せば簡単に設定できます。もしもHTMLで引用するのであれば、
<blockquote><p>引用文</p></blockquote>
のように記述します。引用元がWEB上の文章であれば、そのURLをcite属性の値として
<blockquote cite=”URL”><p>引用文</p></blockquote>
このように使用できます。
信頼のある情報源を使用する
引用や参考をする場合は、信頼性のある情報源を使用しましょう。これにより文章の信憑性を上げられるだけでなく、SEO効果も期待できます。
たとえば、個人ブログや施設のコラムなど、情報の信頼性が担保できるか疑わしいサイトを引用したり参考したりするのは望ましくありません。官公庁や公益法人、研究機関などの信頼性が高い情報源を使うのがよいです。
まとめ
文字数そのものは、ランキング順位を決める決定的な指標ではありません。
しかし、ユーザーの求める情報をしっかりと盛り込んでいくと自然と文字数が増えていきます。
文字数の量にこだわるよりも、ユーザーの求める答えを予測しつつ質の高い記事を作っていくことが、SEO効果を高める近道です。
関連