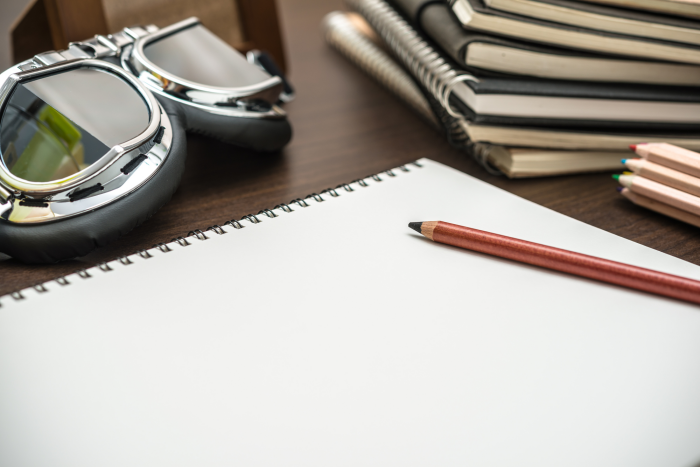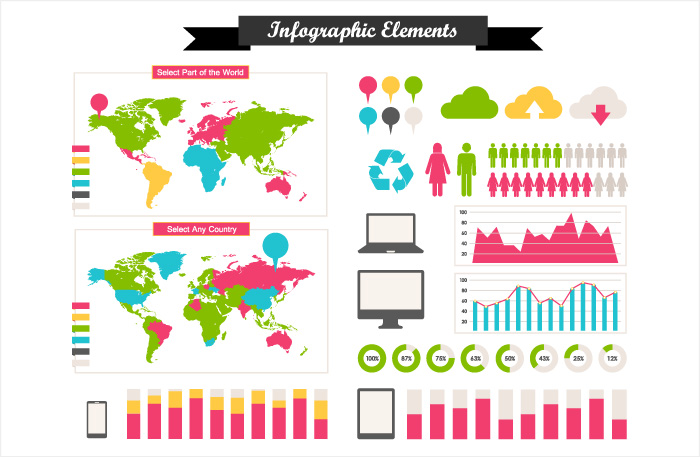本文へ誘導するリード文の書き方!コピペOKのテンプレートつき
2021.04.23
ユーザーを本文へと誘導するリード文(冒頭文・導入文)の書き方をご存知ですか?中には、「書き出しが思いつかない」「上手くまとまらない」という方も多いようです。そこで今回は、リード文の重要性・目的・役割を踏まえたうえで、効率的な書き方や応用できるテンプレートをご紹介します。
そもそもリード文とは?
リード文とは、コンテンツごとに設ける「冒頭文」または「導入文」のことです。
本文に入る前にコンテンツの概略をまとめたリード文を設けることで、短時間で「この記事には何が書かれているのか」が伝わるため、ほぼ全ての閲覧者が読んでくれます。
リード文を配置する場所に、厳格なルールはありません。
一般的には下記のAが多数派ですが、中にはBを採用しているコンテンツもあるようです。
▼よくあるリード文の配置場所
- A「ページタイトル」と「目次」の間
- B「目次」と「本文」の間
リード文はなぜ重要?3つの目的と役割
ほぼ全ての訪問者が読んでくれるリード文は、コンテンツの価値を左右する重要な要素です。
そもそも、なぜリード文は重要なのでしょうか?
その理由は、リード文の「目的」と「役割」から見えてきます。
▼リード文の目的と役割
- 読む価値があるかユーザーに判断材料を提供する
- 滞在時間の長さが伸びてSEO効果が上がる
- ユーザーからの信頼を獲得する
読む価値があるかユーザーに判断材料を提供する
リード文の目的・役割で最も重要なのが、「読む価値」があるかどうかユーザーに判断材料を提供する、という点です。
特に、スマホやタブレットなどで見ているモバイルユーザーが増えている近年、読者は最短ルートで「知りたい答え」を探しています。
コンテンツにアクセスしてから短時間で「この記事は読む価値がある」「探している答えが見つかりそう」と思ってもらえなければ、あっと言う間に離脱されてしまうでしょう。
その点、記事の内容が1分ほどで把握できる短い概略文にまとめたリード文があれば、瞬時に読むべきか判断できるのです。
▼優れたリード文の特徴
- 短時間で訪問者の理解を助けるヒント
- ユーザーの興味・関心を引いてスクロールさせる「きっかけ」
滞在時間の長さが伸びてSEO効果が上がる
ユーザーが検索したキーワードで自社のコンテンツがヒットしたからと言って、最初から最後まで記事全体を読んでくれる訪問者は、そう多くはありません。
そこで重要なのが「リード文」!優れたリード文ほどSEOにとって重要な滞在時間が長くなるのです。
▼リード文の品質と滞在時間の関係
- 適切なリード文:「最後まで読んでみよう」、「続きが知りたい」
- 不適切なリード文:「他の記事の方がイイかも」、「理解するまで時間がかかりそう」
適切なリード文であれば最後まで読んでもらえる確率がアップするのはもちろん、場合によっては関連コンテンツを見てもらえる可能性も上がります。
ちなみに、リード文なしのコンテンツは「探している答えが掲載されているか分からない」「答えがみつかるまで時間がかかりそう…」というネガティブな印象を与えがちです。
ユーザーからの信頼を獲得する
ネット上では、あらゆる情報が提供されています。
その反面、誰もが自分の意見を発信できるため「信用できる情報」なのか判断しにくいのも事実。
そこで、リード文に下記のような一文を追加することで、記事の「信憑性」をアピールすることができます。
▼信憑性を高める一文
- Googleが〇〇の導入を発表しました。
- マーケティグ担当の○○です。
- 長年Webデザイナーの仕事に携わっていると…。
記事を執筆している担当者の名前や役職、オフィシャル情報であることをリード文に盛り込むことで、信憑性・専門性・権威性の裏づけとなり、「この記事は信用できそう!」と思ってもらえるのです。
リード文の作成方法!含める内容は?
ここからは、具体的なリード文の作成方法について見ていきましょう。
重要となるのは、下記の4つのポイントです。
▼リード文の作成ポイント
- ペルソナ(想定読者)を明確にする
- 何が得られるかを提示する
- 本文を要約するコツ
- リード文の前半にSEOキーワードを入れる
なお、ブログのライティング全般については下記の記事を参照して下さい。
ペルソナ(想定読者)を明確にする
ペルソナ(想定読者)の設定は、全てのビジネスにおける基本です。
そもそも記事を書く際は、どのような人にとって役立つ情報を発信するのか、どんな人が興味を持ってアクセスするのかを想定して書かなければなりません。
設定したペルソナをリード文に含めることで、「自分向けの記事だ!」「探していた情報だ!」と訪問者に気づいてもらいましょう。
▼関連記事
何が得られるかを提示する
「この記事を読んで分かること」を端的に表現するのも、リード文の大切な役割です。
例えば、本記事を読んだ後に得られる下記の情報3つがリード文に含まれています。
▼本記事を読んで得られる情報
- リード文の目的と役割
- 読んでもらえるリード文の作成方法
- コピペできるリード文のテンプレート(型)
本文を要約するコツ
ブログのリード文は、記事で提供する情報・知識を要約して1分ほどで読み終わる短文にまとめるのが理想的です。
記事のコアとなる重要な見出しを3つほど選び、下記のように短くまとめましょう。
▼本文の要約
- 本記事では◯◯について解説します。
- そこで今回は、〇〇の作成方法や例文をご紹介します。
- この記事を読めば〇〇の解決方法が分かります。
リード文に含めたい項目が多い時は文章ではなく、箇条書きでも構いません。
リード文の前半にSEOキーワードを入れる
ユーザーは、特定のキーワードからコンテンツにアクセスしています。
つまり、ユーザーの「検索意図」にあたるターゲットキーワードはリード文の必須要素!訪問者が見た瞬間に気づけるよう、できるだけ前半に含めることで、SEO効果のアップが期待できるのです。
例えば、本記事ではSEOキーワードである「リード文 書き方」を冒頭に配置しています。
リード文の書き方!注意点2つ
リード文は、必要な要素をもれなく含めておけば良いという訳ではありません。
注意点として、下記の2点についても把握しておきましょう。
▼リード文の注意点
- リード文は本文完成後に書く
- リード文は200文字ほど、3~5文ほどでまとめる
リード文は本文完成後に書く!
ブログ初心者にありがちなのが、「リード文を最初に書く」というミスです。
まだ完成していない本文をリード文として要約しようとすると、内容や方向性がズレかねません。
したがって、リード文を作成するタイミングは本文を完成させた後が最適!最初に執筆するより短時間で仕上がるのも大きなメリットです。
リード文の最適な文字数は?
結論から言うと、リード文の文字数に制限はありません。
とはいえ、あまりにリード文が長文だと肝心の「要約」という要素が損なわれ、離脱されかねません。
1分ほどで読み切れる200文字ほどにまとめ、句点(。) で区切るセンテンスは3~5文ほどに留めておきましょう。
リード文の書き方テンプレート
リード文を効率的に執筆するには、テンプレートの活用が有効です。
ここでは、リード文の構成を3つのパーツに分けて解説します。
- 文頭:疑問や悩みの問いかけ/共感文/逆説や結論
- 中間:テーマの事例/現状解説/傾向
- 文末:アクションを促す解決策/メリット
想定読者の疑問・悩みに問いかける(文頭)
最初にご紹介するのは、リード文の冒頭でペルソナへ向けて疑問や悩みを問いかける手法です。
▼今すぐ真似できるテンプレート
- 「リード文は必要ないのでは?」と思っていませんか?
- 「なぜリード文が重要なの?」と疑問に思っていませんか?
- 「リード文が上手く書けない」と悩んでいませんか?
- 「リード文の執筆に時間がかかってしまう」と悩んでいませんか?
冒頭の1文だけで、「誰に向けた記事なのか」「どんな疑問や悩みが解決できるのか」を表現できるのが強みです。
共感を獲得する(文頭)
共感は営業手法の鉄板ですが、もちろんリード文にも通用します。
「〇〇な方も多いでしょう」「〇〇ですよね」と書き出すことで、「私に関係ある記事だ!」と思ってもらえます。
▼今すぐ真似できるテンプレート
- 「いつもリード文の書き出しに迷う」という方も多いでしょう。
- 5分でリード文が完成できたら効率的ですよね。
- ブロガーの多くが思っている「リード文の時短化」。
- 「リード文を考えるのが面倒」と思っている方は珍しくありません。
逆説や結論で興味を引く(文頭)
3つ目にご紹介するのは、「常識だと思っていたことが非常識だった」「正解だと思っていた方法が実は不正解だった」といった逆説や結論から入る方法です。
▼今すぐ真似できるテンプレート
たった5文でリード文が書けるのをご存知ですか?
リード文の最適な文字数をご存知ですか?
リード文は本文の完成後に執筆するのが正解です。
意外な事実、または結論を最初に持ってくるこちらの手法は、ユーザーに「知らなかった」「損をしていた」と気づかせ、興味を持ってもらうのが狙いです。
テーマの事例・現状解説・傾向(中間部)
リード文の中間部分には、テーマの事例・現状解説・傾向などが適しています。
▼今すぐ真似できるテンプレート
- リード文はユーザーの興味を惹きつける効果を持つ反面、記事ごと必要なのが難点。
- 「毎回時間がかかる」「離脱率を下げる方法が分からない」という方も多いようです。
- 中には、書くタイミングを誤解している方も多いようです。
ただし、文頭(つかみ)と文末(本文の要約)だけで200文字に超える場合は、省略しても問題ありません。
ベネフィットやメリットの提示(文末)
最後にご紹介するのが、リード文のメインである「ベネフィット」や「メリット」の提示です。
読んだ後に何が得られるのかを、シンプルかつ直接的な表現で述べておきましょう。
▼今すぐ真似できるテンプレート
- 読んでもらえるリード文の書き方を解説します。
- 初心者でも今すぐ真似できるリード文のテンプレートをご紹介します。
- リード文の重要性や具体的な書き方、失敗しないテンプレートなどをご紹介します。
リード文とメタディスクリプションは同じでもOK?
リード文と検索結果のスニペットとして表示されるメタディスクリプション(meta descriptionタグ)は、性質が非常によく似ています。
本文の内容を要約するという点は共通しているため、リード文とメタディスクリプションを同一にしているコンテンツも珍しくありません。
ただし、リード文とメタディスクリプションとでは文字数制限の有無が異なります。
▼文字数制限の違い
- リード文:基本的に制限はないが、200文字ほどが理想的
- メタディスクリプション:100~120字ほど
まずはリード文を執筆してから余分な文字数をショートカットすると、短時間でメタディスクリプションが完成するので効率的です。
▼関連記事
まとめ
ページにアクセスした検索ユーザーが、タイトルの次に目にするリード文。
リード文が最適化されているほど、本文を最後まで読んでくれる確率(読了率)が高くなります。
とはいえ、無理なく本文へ誘導できる優れたリード文の書き方は、そう難しくはありません。
「離脱率を改善したい!」という方は、今回ご紹介したテンプレートを参考にしてリード文の書き方を工夫してみてはいかがでしょうか。
関連