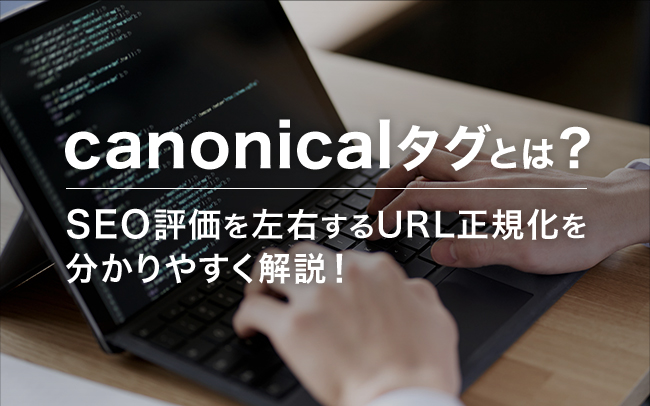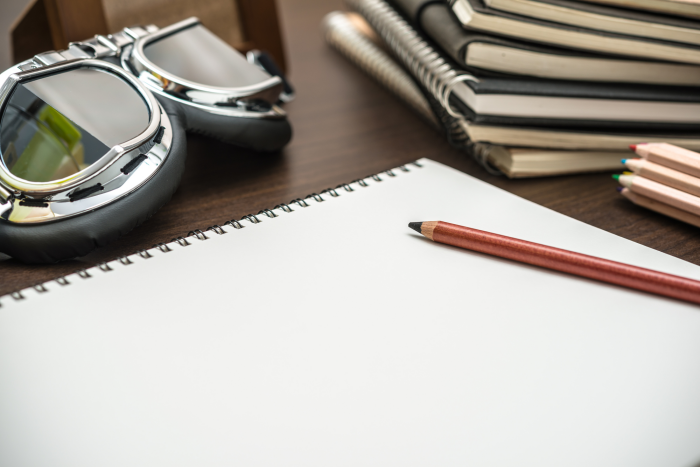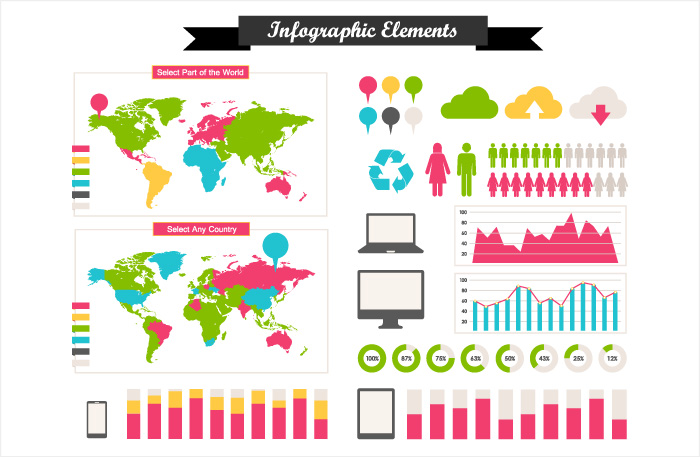canonicalタグとは?SEO評価を左右するURL正規化を分かりやすく解説!
2023.04.06
SEOの内部対策として欠かせないcanonical(カノニカル)タグ。
重複コンテンツによる評価の低下を防いでくれる反面、設定方法をミスすると検索結果から除外されるリスクもあるのです。
そこで今回は、そもそもcanonicalとはどのようなタグなのかを踏まえたうえで、SEO的メリット・設定すべきケース別の書き方・注意点などについてまとめてみました。
canonical(カノニカル)タグとは?
使い方を解説する前に、そもそもcanonical(カノニカル)とはどのようなタグなのかを理解しておきましょう。
▼canonicalタグの基本
- canonicalタグの概要
- なぜURLの正規化が必要なのか?
canonicalタグの概要
canonical(カノニカル)タグとは、同じサイト内に存在する重複コンテンツのURLを1つにまとめる、つまりURLを正規化するために使用するHTMLタグです。
ここで言う重複コンテンツとは、URLおよび内容が「100%同じ」または「極めて似ている」ページの両方を指しています。
そもそもCanonicalとは、日本語に直訳すると「標準的な」「規準的な」を意味する形容詞です。
canonical タグを使ってURLを正規化することで、Googleの検索エンジンに対して「評価して欲しいURLはこれだよ!」と正確に伝えることができるのです。
なぜURLの正規化が必要なのか?
なぜURLの正規化が必要なのか、その理由はSEOにとって不利に働くからです。
▼URLを正規化しないリスク
- SEO評価が複数の重複ページに分散してしまう
- クローラーが重複コンテンツまで巡回する分、最も評価して欲しいページのクロールが遅れる
Googleの検索エンジンは、あくまでURLごとにコンテンツを評価しています。
そのため、たとえ記事の内容が全く同じでも、URLがほんの一部でも異なっているだけで、全く別のページだと認識してしまうのです。
なお、「重複排除システム」はGoogleが2022年11月に発表したランキングシステム一覧に含まれていますので、今後もSEO対策の必須項目と言えるでしょう。
関連記事
「canonicalタグ」と「301リダイレクト」との違いとは?
「301リダイレクト」とは、指定したURLにアクセスした訪問者を転移させるためのコードを指しています。
どちらもURLの正規化によく使われますが、canonicalと大きく異なる点は301リダイレクトの場合、「転送先を指定した元のページが閲覧できない」という点です。
canonicalはクローラーへの提案に使われるタグなので、指定したURL以外のページも閲覧することができます。
一方、301リダイレクトは訪問者を正規URLへと強制的に転送させるため、元ページは閲覧できません。
関連記事
「canonicalタグ」と「301リダイレクト」の使い分け
同一商品のカラーバリエーションが異なるページなど、内容がよく似ているコンテンツを正規化する場合は、canonicalタグの方が適しています。
一方、元ページへのアクセスを完全に遮断したい、または内容が完全に一致しているページ同士を正規化する場合は、canonicalタグよりも強いシグナルを持つ301リダイレクトを設定した方が良いでしょう。
▼URL正規化の使い分け
- Canonical:301リダイレクトが使えない時や、ユーザーが類似URL毎にアクセスする必要がある時
- 301リダイレクト:サーバー移転や、「www」「/」「index.html」などの有無で重複が発生する時
関連記事
canonicalタグの役割とSEO効果
canonicalタグを使ってURLを正規化すべき理由は、下記のようなSEO効果があるからです。
▼役割とSEO効果
- メリット①:重複コンテンツを解消する
- メリット②:評価を1ページに集約できる
- メリット③:クロールの効率が上がる
メリット①:重複コンテンツを解消する
Webサイトを運営していると、止むを得ない事情で重複・類似コンテンツが発生しがちです。
▼重複コンテンツの一例
- 内容が同じスマホ用のページとPC用のページがあり、それぞれURLが違う
- 商品は同じだが、カラーバリエーションごとにページを分けているECサイト
- 間取りは同じだが、階数ごとにページを分けている賃貸サイト
サイト内の同じようなページが検索結果にいくつも表示されてしまうと、ユーザーはもちろん検索クローラーに対しても、どのページがメインなのかが伝わりません。
その点、canonicalで特定のページを指定すれば、正規化されたURLが優先的に検索結果にインデックスされます。
優先して表示したい項目を指定することで、検索クローラーに対して最も重要なURLが正確に伝わるうえ、閲覧ユーザーにとって親切なサイト構造になるのです。
関連記事
メリット②:評価を1ページに集約できる
2つ目のSEO的メリットは、コンテンツの評価を1ページに集約できるという点です。
重複・類似コンテンツは、「書かれている内容に対する評価」だけでなく「被リンク」の効果も分散してしまいます。
Googleの検索エンジンがコンテンツを正しく評価できない状態、と言ってもよいでしょう。
その点、canonicalタグで正規URLを指定しておけば「評価の分散」が防げる分、主要ページが上位表示されやすくなるのです。
メリット③:クロールの効率が上がる
3つ目のSEO的メリットは、効率よくクロールして貰えるという点です。
重複・類似コンテンツが多いほどクローラーへの負荷が増し、クローリングの効率が低くなります。
効率よくクロールしてもらえるよう、複数の重複コンテンツの内、最もアクセスを集めたいページを正規URLとして指定しておきましょう。
canonicalタグが必要な9つのケース
ここからは、canonicalタグを設定すべき代表的な9つのケースについて解説します。
▼canonicalタグが必要なケース
- 「PC用」と「スマホ用」でURLが異なる
- AMPページ
- ECサイトの類似ページ(自動生成)
- 計測用パラメータ付きのURL
- 広告用ランディングページ
- ABテストをする場合
- コンテンツが複数ページにまたがっている
- 301リダイレクトが使えない場合
- 自己参照canonical(シンジケーション)
「PC用」と「スマホ用」でURLが異なる
コンテンツの内容が同じでも、URLがデスクトップ向けサイトとスマホサイトで異なる場合は、クローラーに重複コンテンツだと認識されてしまいます。
▼デバイスごとにURLが異なっているケース
- PCサイト:https://www.example.com/pc
- スマホサイト:https://www.example.com/sp
この場合、canonical(カノニカル)タグとalternate(オルタネイト)タグの両方を使って、お互いの存在を示す「アノテーション」を設定します。
PCページにはスマホページの存在がクローラーに伝わるよう、HTMLの<head>内にalternateタグを記述しましょう。
▼PCページに設定するalternateタグの書き方
<link rel="alternate" media="only screen and (max-width: 640px)" href="http://www.example.com/sp">
一方、スマホページにはPCページの存在がクローラーに伝わるよう、同じくHTMLの<head>内にcanonicalタグを記述します。
▼スマホページに設定するcanonicalタグの書き方
<link rel="canonical" href="https://www.example.com/pc">
詳しくは下記の記事を参照して下さい。
関連記事
AMPページ
モバイル端末で高速表示させるAMPを実装すると、同一のコンテンツに対してAMP用のページと非AMP用のページの2つがサイト内に存在することになります。
そのためcanonicalを利用したURLの正規化が必要です。
AMP実装ページとAMP非実装ページにはそれぞれ、次のように記述しましょう。
▼AMP実装ページ
<link rel="canonical" href="AMP非実装ページのURL">
▼AMP非実装ページ
<link rel="amphtml" href="AMP実装ページのURL">
なおAMPについては次の記事で詳しく解説しています。
関連記事
ECサイトの類似ページ(自動生成)
ECサイトで服を選ぶ際に、カラーやサイズによってページが複数ありますよね。
これはコンテンツの内容はほぼ同じですが、ページのURLと掲載されている画像が異なっている状態で、使用しているシステムによっては自動的に類似コンテンツが生成されているECサイトも少なくありません。
商品の基本情報や解説など、コンテンツ内容の大部分が同じでもURLが違う場合は、それぞれ別のコンテンツと認識され、Googleから重複ページとして評価されてしまうため、代表のページを1つに決めてcanonicalタグでURLの正規化を行いましょう。
関連記事
計測用パラメータ付きのURL
web広告やアフィリエイト広告を掲載しているサイトでは、流入アクセス解析のために計測用パラメータをURLに付与されています。
この場合もクローラーに本来の正規ページを評価してもらえるよう、canonicalタグでURLの正規化が必要です。
関連記事
広告用ランディングページ
ウェブサイトとは別に広告用にランディングページ(LP)を作成することがありますが、ランディングページとウェブサイト内のコンテンツが重複することは少なくありません。
この場合も、URLの正規化を行う必要があります。
noindexを利用する方法もありますが、ランディングページに被リンクを受ける場合を考えて、canonicalを使用するのがおすすめです。
関連記事
ABテストをする場合
アクセス数や成約数などが比較できるよう、特定の箇所以外が同じコンテンツのページを設けてABテストを行っている場合、重複コンテンツと判断される可能性が高いです。
どちらか一方のURLをcanonicalで正規化しておきましょう。
コンテンツが複数ページにまたがっている

複数のページにまたがる続き物のコンテンツに、個別ページの他に全てを表示するページ(view all page)がある場合、canonicalを利用することがあります。
以前は複数のページにまたがる続き物のコンテンツには、「rel=next/prevタグ」を利用することで、重要なページを検索結果に表示させることができました。
しかし2019年3月21日に、rel=next/prevのサポートが数年前から終了していることをGoogleは発表しており、現在は利用してもGoogleがサポートしていないため、設定する意味がありません。
続き物のコンテンツの中に全てを表示するページがある場合、「全てを表示するページ」をcanonicalタグで正規化することで、他のページで獲得したSEO効果を「全てを表示するページ」に集約し、「全てを表示するページ」が上位表示されやすくなります。
なお全てを表示するページをcanonicalタグで正規化した場合、他の個別ページは検索結果に表示されなくなることに注意しましょう。
rel=next/prevのサポート終了については次の記事で詳しく解説しています。
関連記事
301リダイレクトが使えない場合
「サイトの移転」「サイト名の変更」「サーバー移転」など、ドメイン変更に伴うURLの正規化で最も推奨されているのは、SEO評価が引き継げる301リダイレクト設定です。
ただし、サーバー事情などで301リダイレクトが設定できない場合は、canonicalタグを代用しましょう。
▼旧サイトのHTML<head>内に記述するコード
<link rel="canonical" href="新サイトのURL">
自己参照canonical(シンジケーション)
自己参照canonicalとは、HTMLファイルは1つしか無いが、アクセスできるURLは複数ある場合に行う正規化の方法です。
自身または他者によって行われる、シンジケーション(記事配信)の対応策と言った方がイメージしやすいかもしれません。
▼該当ケース
- メールマガジンからの流入を計測するパラメータを、運営者がURLに付与している
- 「SNSでの共有」や「外部からのリンク設置」により、意図しないパラメータがURLに付与されている
この場合も検索クローラーに重複コンテンツとして扱われないよう、あらかじめ正規URLに自己参照canonicalを設定しておく必要があります。
オリジナルページ、つまり正規URLのHTML<head>内にcanonicalタグを設置して、自身のURLこそが評価対象だとクローラーに示しておきましょう。
▼自己参照canonicalの記述例
<link rel="canonical" href="正規URL">
自己参照canonicalタグを用いてクローラーに「自サイトのオリジナル記事」だと宣言しておけば、まとめサイトなどの第三者によって二次配布されたコンテンツの影響で、トラフィックが減少するリスクを回避できます。
canonicalタグの適切な使い方
ここからは、canonicalタグの設定方法について解説していきます。
▼canonicalタグの設定方法
- canonicalタグの設置場所
- canonicalタグの書き方
canonicalタグの設置場所
canonicalタグを記述する場所は、下記2種類から選べます。
▼canonicalタグの設置場所
最も一般的なのは、コンテンツの内容部分にあたる<body>ではなく、ページの情報を記載する<head>内に設定する方法です。
また検索エンジンのクローラーは、ページの構造を上から順に見ていきますので<head>内でも、できるだけソースの上の方にcanonicalタグを記述しましょう。
canonicalタグの書き方
ここでは、canonicalタグの書き方について4つの項目に分けて解説します。
▼canonicalタグの書き方
- Googleは絶対パスを推奨
- HTMLに記述する方法
- HTTPヘッダーに記述する方法
- WordPressで設定する方法
Googleは「絶対パス」を推奨
絶対パスとは、リンク先URLを「https://」も含んでそのままフルで記述することを言います。
これに対し、相対パスとは「https://」を省きファイルの場所だけを指定する記述方法です。
▼絶対パスと相対パスの違い
- 絶対パス:https://pecopla.net/seo-column/canonical-tag/
- 相対パス:/seo-column/canonical-tag/
相対パスでは正常に作動しない場合があるため、Googleは絶対パスで記述することを推奨しています。
関連記事
HTMLに記述する書き方
canonicalタグを設定するには、ページソースの<head>内に絶対パスを用いて下記のように記述します。
▼記述例
<head>
<link rel="canonical" href="正規化したいURL">
</head>
実際に記述してみると下記のようになります。
<link rel="canonical" href="https://pecopla.net">
これをソースの<head>内に記述します。
HTTPヘッダーに記述する書き方
一方、PDFファイルなどHTML以外で正規化を行う場合は、同じく絶対パスを用いてHTTPヘッダーに下記のコードを記載しましょう。
▼記述例
Link:<http://評価を集中させたいページのURL>; rel="canonical"
WordPressで設定する方法
WordPressを使用している場合は、canonicalタグが自動で設定できる「All in One SEO Pack」というプラグインがおすすめです。
▼設定手順
- プラグインを有効化する
- ダッシュボードのメニューから「All in One SEO Pack」を開く
- 「一般設定」を選択
- 「Canonical URL」という項目にチェックを入れる
ちなみに、「投稿ページ」や「固定ページ」を指定してcanonicalタグを設定する場合の手順は、下記の通りです。
▼個別にcanonicalタグを設定する手順
- 「カスタム Canonical URL を有効化」にチェックを入れる
- ページ作成画面下部に「canonical指定先URLを追加する項目」が追加される
- 対象ページのURLを入力する
canonicalタグの注意点
canonicalはURLの正規化に非常に有効なタグですが、使い方を誤ってしまうとSEOに逆効果になってしまうことがあります。
canonicalを適切に使うためには、下記の注意点を漏れなく厳守しなければなりません
▼注意点
- 記入ルールを守らないと検索結果に表示されない
- 内容が異なるコンテンツには使用しない
- canonicalタグが設置できるのは1ページに1つだけ
記入ルールを守らないと検索結果に表示されない
1つ目の注意点は、基本的な記入ルールについてです
▼canonicalタグの記入ルール
- HTMLの<head>内に記入するのが基本
- 相対パスではなく、絶対パスで記述する
- URLの指定先を間違えない
canonicalタグの記述を間違えると、canonicalタグを間違って指定したページが検索結果に出なくなるため注意が必要です。
内容が異なるコンテンツには使用しない
たとえば、ページ1とページ2という内容の異なるページがあったとしましょう。
この時ページ2に次のようなcanonicalタグを指定してしまうと、ページ1が正規化されてしまい、ページ2は検索結果に表示されなくなります。
<link rel="canonical" href="http://example.com/1.html">
なお、内容が大きく異なるページにcanonicalタグのURLが設定されている場合、Googleはその記述を無視するケースもあります。
しかし、301リダイレクトには及ばないもののcanonicalは強いリクエストのため、記述通りにページ1が正規化されて、ページ2が表示されなくなることが多いのです。
canonicalタグが設置できるのは1ページに1つだけ
1ページ(1つのHTMLファイル)に対し、2つ以上のcanonicalタグは設置できません。
1つ目ともども検索エンジンから無視されてしまいため、設置できるcanonicalタグは1ページにつき1つだけと覚えておきましょう。
とくにWordPressを使用しているWebサイトは要注意!canonicalタグがデフォルトで自動設定されるプラグインやテーマも多いのです。
canonicalタグが重複しないよう、あらかじめソース画面などで確認してから設定しましょう。
canonicalタグのチェック方法
ページをウェブに公開する前に、canonicalタグが正しく設定されているかチェックしましょう。
▼チェック方法
- Google Search Consoleでチェックする
- Google Chromeの拡張機能でチェックする
- HTMLでチェックする
Google Search Consoleでチェックする
canonicalタグを設定した後、Google がどのページを正規と見なすか確認するには、Google Search Consoleの「URL 検査ツール」を使用します。
確認したいページのURLを入力後、「カバレッジ」をチェックしてみましょう。

一致していない場合は、ページ自体またはサイト構造など問題点がどこにあるか調査する必要があります。
関連記事
Google Chromeの拡張機能でチェックする
Google Chromeが拡張機能として無料で提供されている「Checkbot」でも、正規化URLの設定が正しいかどうか確認することができます。
Google Search Consoleがおススメですが、使用できない場合は「Checkbot」で確認してみましょう。
HTMLでチェックする
手動ではあるものの、ブラウザからhtmlソースを確認するのも1つの方法です。
ただし、下記の通り全ての工程を手動で行う必要があるため、時間をかけたくない方は前述した「Google Search Console」または「Google Chromeの拡張機能」を試してみましょう。
▼HTMLでチェックする手順
- 該当ページを開く
- ブラウザ上で右クリックし、「ページのソースを表示」を選択
- 表示されたHTMLソースから、「<link rel=”canonical”」の文字を検索する
- 記述ミスがないか確認する
まとめ
canonical(カノニカル)とは、同一または類似の重複コンテンツを排除し、検索エンジンのクローラーに対して評価して欲しい正規のURLを伝えてくれる便利なタグです。
canonicalタグの適切な使用法さえマスターすれば、重複コンテンツによるペナルティを回避しながら、サイトに訪れる検索ユーザーにとって親切なサイトを作ることができます。
サイト運営をしていると似たようなテーマや商品を取り扱う機会に遭遇しがちですが、そのような時こそcanonicalタグの出番です。
ただし、設定方法を間違えると検索順位の低下につながるため、ぜひ本記事でご紹介したノウハウを参考にしてみて下さい。
関連