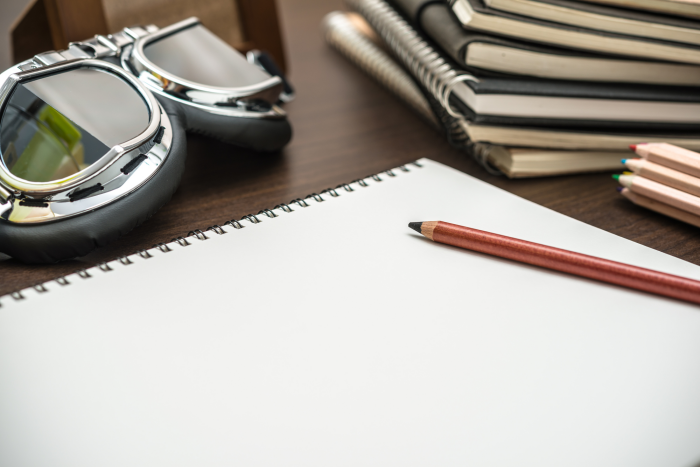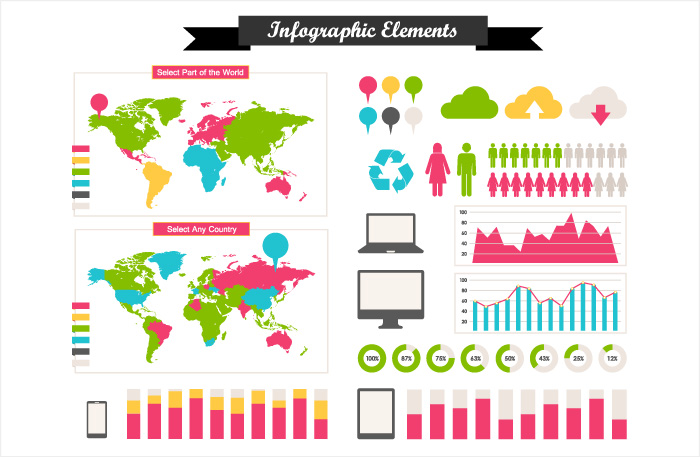失敗しないドメインの選び方とは?SEOとの関係を6つの視点で解説
2025.06.25
Webサイトやブログを開設する際に欠かせないのがドメインです。
しかし、中にはSEOに不利に働くタイプもあるため、正しい選び方を理解していなかったばかりに検索順位が上がらず変更を余儀なくされるサイトも珍しくありません。
そこで本記事では、ドメインの種類・SEOへの影響を踏まえたうえで「失敗しない選び方」を詳しく解説します。
ドメインとは?区分と構成要素
ドメイン(domain)とは、数字の羅列で構成されているIPアドレスを人間が視認しやすい英語や日本語で表したインターネット専用の住所で、WebサイトのURLやメールアドレスに含まれています。
▼該当箇所
- WebサイトのURL:「https://」以降の文字列
- メールアドレス:「@」以降の文字列
あくまで固有の住所ですから、同じドメインのWebサイトやメールアドレスはインターネット上に存在しません。
例題として、当ぺコプラのトップページ「https://pecopla.net」を区分してみましょう。
▼区分と構成
- プロトコル:https://
- 任意のドメイン名:pecopla
- トップレベルドメイン(TLD):.net
上記の通り、メインサイトのトップページなどはシンプルかつ短いURLが一般的で、少なくとも2種類の区分で構成されています。
本ドメイン・サブドメイン・サブディレクトリの違いとは?
「https://以降の文字列」、「TLDが必須」という2点は共通しているものの、大本となるメインサイトか補足的なサイトかによってドメインの「表記」と「区分」が異なります。
- 本ドメイン(メインサイト/本家):https://pecopla.net
- サブドメイン(メインの系列/分家):https://sub.pecopla.net
- サブディレクトリ(メイン内/本家の一室):https://pecopla.net/seo-column
当ページのURLが「https://pecopla.net/seo-column/domain-seo」になっているのは、サブディレクトリを採用しているからです。
ちなみに、Googleのジョン・ミューラー(John Mueller)氏がアナウンスしている通り、「サブドメイン」と「サブディレクトリ」にSEO効果の差はありません。
▼参考サイト
トップレベルドメインとは?
トップレベルドメイン(TLD:Top Level Domain)とは、ドメインネームシステム(DNS :Domain Name System)というインターネット階層の最上位にあたる識別名です。
TLDを大きく分類すると下記の2種類に分けられ、それぞれに複数のトップレベルドメインが存在します。
- ccTLD(country code Top Level Domain):国別コード
- gTLD(generic Top Level Domain):分野別コード
ccTLD(国別)の種類と特徴
ccTLDとはcountry code Top Level Domainの頭文字を取った略称で、ISO(国際標準化機構)の規定に則り国および特定の地域に割り当てられた二文字の識別コードです。
▼ccTLDの一例
- .jp:日本
- .us:アメリカ合衆国
- .kr:韓国
- .cn:中国
2021年3月時点で255種類のccTLDが存在しており、一般社団法人 日本ネットワークインフォメーションセンターの公式サイトで一覧が公開されています。
「.jp」の種類と特徴
日本を対象とした「.jp」には下記の3種類があり、取得対象と数制限に違いがあります。
▼「.jp」の種類と取得する際の注意点
|
取得対象 |
数制限 |
| 汎用JPドメイン名 |
日本の住所を持つ組織・個人 |
なし |
| 都道府県型JPドメイン名 |
日本の住所を持つ組織・個人 |
なし |
| 属性型(組織種別型)JPドメイン名 |
登録資格を満たす組織 |
一つの組織に一つだけ |
ちなみに、日本の住所を持つ個人・病院・組織を対象とした「地域型JPドメイン名」の新規登録受け付けは、2012年3月31日で終了しています。
代替えとして2013年に追加された地理的トップレベルドメイン(GeoTLD:Geographic top-level domain)は、「.tokyo」などエリアがより具体的にイメージできるのが最大の強みです。
属性型(組織種別型)JPドメイン名の種類と特徴
属性型(組織種別型)JPドメイン名の最大の特徴は、取得対象が登録資格を満たす企業・組織だけに限定されているという点でしょう。
なおかつ1つの組織で複数取得が禁じられており、中には「.co.jp」のように登記簿謄本が必要なタイプもあります。
したがって、たとえ日本の住所を持っていても個人や個人事業主は取得できません。
▼属性型(組織種別型)JPドメイン名の一例
- .co.jp:株式会社、有限会社/合同会社/投資法人/企業組合など
- .or.jp:財団法人/社団法人/医療法人/宗教法人/企業組合など
- .ne.jp:日本国内のネットワークサービス提供者など
「.co.jp」の場合、「.co」がセカンドレベルドメイン(SLD:Second-level domain)にあたります。
gTLD(分野別)の種類と特徴
gTLD(分野別)とは、generic Top Level Domainの頭文字を取った略称で、どの国に住んでいるユーザーでも取得できるのが特徴です。
gTLDには世界中で最も利用率が高い「.com」をはじめ、用途別に様々な種類があります。
|
主な用途 |
登録対象と特徴 |
| .com |
商業組織用 |
本来は商取引事業者だが、サービス名としても利用される事が多く、特に使用・用途に制限がない。 |
| .net |
ネットワーク用 |
元々はインフラのためのものだが、現在では.comと同じく使用・用途に制限がない。 |
| .org |
非営利組織用 |
元々は非営利団体用だったが、現在では.comと同じく使用・用途に制限がない。 |
| .info |
制限なし |
現在では、情報サイト以外も使用が可能。 |
| .biz |
ビジネス用 |
実際には用途制限はなく、誰でも利用可能。 |
| .name |
個人名用 |
個人名と無関係であっても、「△△.name」というドメインが取得可能。 |
| .pro |
弁護士、医師、会計士、エンジニア等用 |
2004年11月8日にエンジニアが追加され、2015年11月16日から世界の誰でも登録可能になった。 |
| .xxx |
アダルト用 |
アダルトサービス提供者 |
ドメインがSEOに与える影響とは?
ドメインを選ぶ際、Webサイトの運営者にとって最も気がかりなのがSEOとの関係性でしょう。
最適な選び方を理解していなければ、Googleから「上位表示するに値しないサイト」だと判断され兼ねません。
そこでこの段落では、ドメインの正しい選び方を理解するうえで欠かせないSEOとの関連性を、6つの視点から解説します。
トップドメインの種類によってSEO効果は変わるのか?
結論から言うと、gTLDであればメジャーな「.com」であろうとマイナーな「.ninja」であろうとSEO効果に差はありませんが、ccTLDにおける国の不一致はSEOにとって不利に働きます。
その根拠となっているのが、2016/06/14に配信されたEnglish Google Webmaster Central office-hours hangoutの動画です。
Googleのジョン・ミューラー(John Mueller)氏は、上記の動画で下記の2点について明言しています。
- gTLD(分野別トップレベルドメイン)のSEO効果は全て同等で、どの種類を選んでも検索順位に影響しない
- ccTLD(国別コードトップレベルドメイン)が不一致の場合は、SEOにネガティブな影響を与える
また、同じくGoogleのマット・カッツ(Matt Cutts)氏もウェブマスターフォーラムにてccTLDの正しい選び方について言及しています。
上記の動画を要約し、注目すべきポイントをピックアップしてみました。
- GoogleはccTLDによってWebサイトが所属している国や地域を判断している
- 米国のサイトに「.jp」が使われていると、日本のサイトだと誤認されがち
つまり、SEOに影響しないgTLDであれば選び方に悩む必要はありませんが、ccTLDの選び方を間違うとSEOにとって致命的な痛手を被り兼ねないのです。
トップレベルドメインのイメージはSEOに影響する?
Googleがアナウンスしている通り、gTLDは用途の整合性さえ間違っていなければ種類によってSEO効果に差が生じることはありません。
とは言え、ドメインには固有のイメージが定着しているため、間接的にSEO効果に影響を与えているのが実情です。
多くのユーザーは、トップレベルドメインによってWebサイトの価値をイメージし、評価の基準にしています。
例えば、利用率が低い「.co」や「.xyz」には低コストというメリットがあるものの、世界的にメジャーな「.com」や「.net」の方が信用できるというユーザーがほとんどです。
つまり、選び方で失敗しないためにはドメインが持つイメージも考慮すべき要素と言えます。
キーワードを含む独自ドメインはSEOに効果的?
世界で1つだけのオリジナル性を出せるのが、独自ドメインの最大の強みです。
好きな文字列が使えるためターゲットキーワードを含めることも可能ですが、爆発的なSEO効果は期待できません。
なぜなら、GoogleがSEOを評価する際に最も重視しているのは、あくまでコンテンツの内容であってドメインの文字列ではないからです。
その証拠に、ドメインに主要キーワードが含まれていないWebサイトが、検索結果の上位に表示されるケースも珍しくありません。
中古ドメインはSEOに効果的?
結論から言うと、自サイトとの相性が良く高い品質を備えた中古ドメインであれば、新規ドメインよりもSEOにポジティブな影響を与えます。
▼中古ドメインがSEOに強い理由
- インデックススピードが速い
- ドメインエイジが引き継がれる
- ページランクの実績が引き継がれる
- 被リンクが引き継がれる
ただし、いくつかのデメリットもありますので、選び方によっては逆効果にもなります。
詳しくは下記のコラムを参照してください。
日本語ドメインはSEOに効果的?
かつては、Webサイトのジャンルが伝わりやすいというメリットから、日本語ドメインがSEOに有利だと評価されていました。
ところが、下記のデメリットを重視したGoogleがEMD (Exact Match Domain) アップデートを実施して以降、「ドメイン名と検索クエリの完全一致」だけを理由に上位表示されなくなったのです。
▼Googleが問題視したポイント
- たとえコンテンツ内容が低品質であっても上位表示されやすい
- 漢字、平仮名、カタカナが「文字化け」する
- 海外ユーザーにとっては分かりにくい
したがって、日本語のキーワードをドメインに含めても大きなSEO効果は期待できません。
「.tokyo」などの新gTLDはSEOに効果的?
エリアに特化した「.tokyo」や、業種に特化した「.hair」など、次々と新gTLDが増えています。
確かに、ジャンルの分かりやすさや目新しさからくるインパクトは大きなメリットではあるものの、だからと言ってSEOに有利という訳ではありません。
その根拠となっているのが、公式サイトに記載されているGoogleのアナウンスです。
検索に対する影響
新しいドメイン末尾を使っても、検索結果に影響はありません。Google でも他の検索エンジンでも、すべての TLD は平等に扱われます。新しい TLD が検索エンジンのランキングに影響を与えることも、検索結果の下の方に掲載されることもありません。
引用:Google Domains
SEOに有利なドメインの選び方
この段落では、SEOとの関係性を踏まえたうえで最適なドメインの選び方について解説します。
メジャーなタイプを選ぶ
利用率・信用度・覚えやすさの3つを基準にするのも、ドメインの賢い選び方です。
そもそも、ドメインには新旧を問わずメジャーかマイナーかによって下記のような違いがあります。
▼メジャーとマイナーの違い
- メジャーな「.com」や「.net」:高価な反面、利用率・信用度が高く覚えてもらいやすい
- マイナーな「.co」や「.xyz」:安価な反面、利用率・信用度が低く覚えにくい
まして、提供が始まって間もない新gTLDであれば、信用度の低さや覚えにくさがSEOにおいてマイナスに作用する可能性は十分にあります。
つまり、最も無難でSEOに悪影響を与えないのはメジャーなドメインなのです。
もちろん、選び方の要素として価格だけを重視するのは避けるべきでしょう。
ジャンルとトップレベルドメインのイメージを一致させる
ドメインが持つ固有のイメージは、ユーザーに安心感を与えることもあれば、反対に不信感を抱かせることもあります。
特に「サイトのジャンル」と「トップレベルドメインが持つイメージ」が著しく異なる場合、「フィッシング詐欺などのサイバー犯罪では?」と怪しむ閲覧ユーザーも少なくありません。
確かに、gTLDの用途や登録対象者は以前に比べて柔軟になっていますが、やはりSEO的には「主な用途」に合わせた方が良いでしょう。
「サイトのジャンル」と「トップレベルドメインが持つイメージ」が一致しやすくなるため、ユーザーからの信用を得るには欠かせない選び方ポイントです。
また、一定の信頼性が担保されているとユーザーに印象づけるには、審査を通過した人だけが取得できるが「.co.jp」や「ne.jp」などが有力候補になります。
「新規ドメイン」と「中古ドメイン」のどちらにするか
「今すぐ上位表示させたい」「0から対策するスキルがない」という場合は、すでに高いSEO評価を獲得している中古ドメインがおすすめです。
月々のランニングコストは割高ではあるものの、下記の条件を満たしていれば短期間での上位表示が期待できます。
▼中古ドメインの選び方
- 自サイトとテーマまたはジャンルが同じだった
- 高品質の被リンクが多い
- Googleからペナルティや警告を受けていない
一方、何よりオリジナリティを重視したい方は新規ドメインが最適です。
後述しますが、任意のドメイン名を工夫することでSEO効果を引き出してみましょう。
SEOに強い任意ドメイン名の選び方
新規で取得する場合、任意ドメイン名の文字列にも選び方のコツがあり、特に重要なのが2つの大原則です。
▼2大原則
- サイトのテーマやジャンル、内容が伝わりやすい文字列
- 覚えてもらいやすい文字列
ちなみに、当サイトであれば「https://pecopla.net」に含まれている「pecopla」が任意ドメインにあたります。
社名やブログ名と同じ文字列にする
社名をそのまま使う、またはブログ名と同一にすることで下記のメリットが生れます。
▼メリット
- 会社の業務内容が、そのままサイトのテーマとして伝わる
- 最小限の文字数で覚えやすい
当社のように本サイトとブログの両方に共通点となる社名を入れておくだけで、関連性がダイレクトに伝わるという二次的メリットも大きな強みです。
- 本サイト:https://pecopla.net
- ブログ(サブディレクトリ):https://pecopla.net/seo-column
ただし、社名やブログ名を変更した場合は関連性が崩れるため、ドメインも変更した方が良いでしょう。
運営者の名前と同じ文字列にする
法人名やブログ名が決定する前にサイトを開設する場合は、運営者の名前をそのまま使う方法がオススメです。
ドメインと紐づいているのはあくまで個人名ですから、社名やブログタイトルを後付けで決めようが変更しようが、支障はありません。
そのため、任意ドメインの選び方として「有名ブロガー」や「個人事業主」に多用されています。
ただし、将来的に変更しなくて済むように「実名」を公開するか、もしくは弊害が少ない「ニックネーム」にするかは、明確にしておきましょう。
ジャンルやキーワードを文字列に含める
前述した通り、ドメインにジャンルやテーマを表すキーワードを含めても、直接的なSEO効果はありません。
とはいえ、「ユーザビリティの向上」と「運営のしやすさ」の両面が有利になるため、間接的なSEO効果が期待できます。
▼メリット
- 閲覧ユーザーに内容が伝わりやすく、覚えてもらいやすい
- 社名やブログ名を変更しても、実名からニックネームに変更しても問題ない
ただし、同じジャンルやテーマを取り扱っている競合サイトが多い場合は、希望する文字列が既に使われている可能性が高いというデメリットがあります。
競合サイトと同じ文字列は使わない
任意ドメインの文字列を選考する際、多くの方が競合サイトを参考にするでしょう。
しかし、たとえTLDだけを変更しても文字列が100%同じ、あるいは酷似している場合はSEOにとって逆効果になり兼ねません。
紛らわしい文字列はWebサイト自体の認知が低下するリスクを伴うだけでなく、ユーザーに「悪意あるサイト」と誤解されがちなのです。
おすすめのドメイン取得サイト3選
提供サイトの選び方も、ドメインを決める際の重要なポイントです。
この段落では、ユーザーの満足度が高いおすすめの3社をピックアップしてみました。
お名前.com

出展:お名前.com
GMOインターネット株式会社が運営する「お名前.com」は、個人・法人を問わず高いシェアを誇っている業界大手の1つ。業界最安値を謳っていますが、さらにお得に取得したい方はセールやキャンペーンを併用してみましょう。
▼人気の理由
- TLDの網羅性が高く、580種類以上から選べる
- 新規でも中古でもOK
- 電話サポートから商標保護まで、サービスが充実している
- 東証一部上場企業が運営している安心感
Xdomain

出展:Xdomain
コスパを重視する方には、取得費用だけでなく更新費用の安さにも定評がある「Xdomain」がおすすめ。運営元がエックスサーバー株式会社なので、レンタルサーバーとセットになったお得なキャンペーンも人気です。
▼人気の理由
- 「.com」など、人気ドメインの価格が業界トップクラス
- 「.jp」でも、登録者名含めた全情報を代理公開してくれる
- 電話サポート対応で、初心者でも安心
ムームードメイン

出展:MuuMuu Domain
運営元は複数の関連サービスを一手に提供しているGMOペパボ株式会社。管理画面の見やすさ、追加オプションの豊富さも魅力です。
▼人気の理由
- 「ロリポップ」のレンタルサーバーとセットで契約するとドメインが無料
- 誤操作やサイトの乗っ取りが防げる「ドメインロック」が年間1,200円
- リアルタイムで相談できるチャットがあるので、初心者にも安心
まとめ
GoogleはccTLDを除く全てのTLDを平等に評価していると明言していますので、基本的には何を選んでも検索ランキングに直接的な影響はありません。
したがって、ドメインの選び方で優先すべきなのは「認知度」と「ユーザーに対する利便性」の2点に絞るべきでしょう。
SEO効果は各ドメインに紐づいているため、そう簡単に変更はできません。
だからこそ、ぜひ長く愛用できるドメインを厳選して下さい。
関連