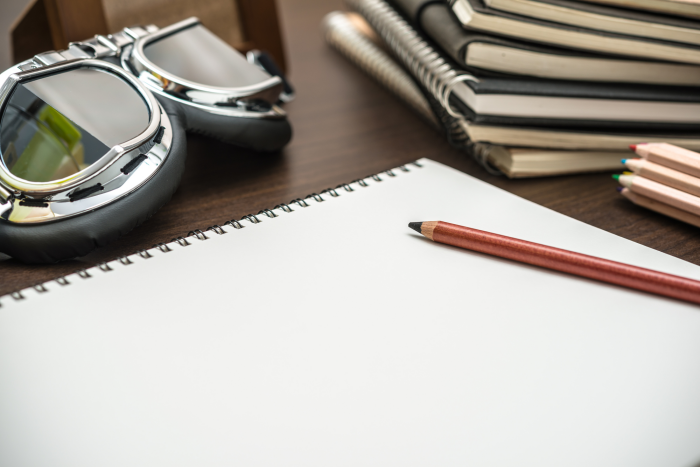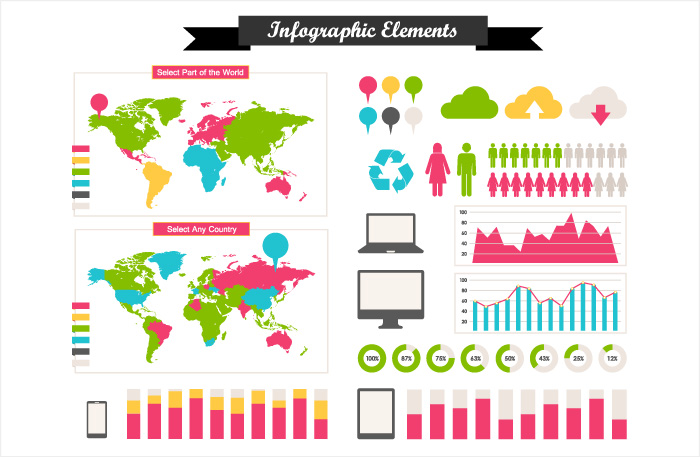カテゴリ分けはSEOに重要!カテゴリ分けのポイントや注意点を解説!
2025.07.10
SEOの効果を高めるサイトを制作するためには、カテゴリ分けは重要です。サイト制作時にしっかりとカテゴリ分けを行うことで、ユーザーの利便性やクローラーの巡回率につながりSEO効果を高めます。
当記事ではSEO効果を高めるために必要なカテゴリ分けのポイントや注意点について紹介していきます。サイトやブログの立ち上げを考えている方はぜひ参考にしてください。
カテゴリ構造の基本を理解しよう
この項目ではまずはカテゴリと理想的なカテゴリ構造について紹介していきます。
カテゴリとは?
カテゴリとは種類や区分といった意味を持つ言葉です。Webサイトでいうカテゴリとは、ユーザーに分かりやすいようにジャンルやタグごとに分けることをいいます。
例えば自動車を取り扱っているサイトの場合は、次のようなカテゴリ設定を行います。
「自動車→軽自動車・SUV→メーカー・車種」
このように自動車という親のカテゴリに軽自動車やSUVというように種類ごとに子のカテゴリを設定するイメージです。カテゴリ分類を行うことでユーザーが欲しい情報を見つけやすくなります。
理想的なカテゴリ構造
前の項目で、カテゴリ分けについて簡単に紹介しました。このように、種類ごとに「第一階層→第二階層→第三階層」というような綺麗なツリー構造であり、1つのカテゴリに大きな偏りなくまた深い階層にしないことが理想的なカテゴリ構造です。
また、第一階層のカテゴリは広く大きなくくりのカテゴリを設定し、下の階層になるほどより詳細な細かいカテゴリを設定しましょう。

カテゴリごとに分けて階層構造にしたものを、ディレクトリ構造とも呼びます。無駄なページを省いて、シンプルに広く浅く設計するとよいでしょう。
▼関連記事
カテゴリ分けはSEOに直結する
結論から申しますとカテゴリ分けとはWebサイトの構造そのものです。そのため、分かりやすいカテゴリ構造(サイト構造)とすることで、ユーザーの利便性の高いサイト、使いやすいサイトとなります。
サイトの利便性はSEOにも影響を与えるため、カテゴリ分けはSEOにも影響するのです。
反対にカテゴリ分けがしっかりしていないと、ユーザーの利便性が欠け、またクローラーが巡回しにくいためどれだけ良質な記事を書いても検索エンジンに正しく評価されにくい状態となってしまいます。
SEOを高めるためには、正しいカテゴリ分けを行うことが大切です。
カテゴリ分けのポイント
次にカテゴリ分けのポイントについて、5つ紹介します。上述したようにカテゴリ分けはSEOに直結するためポイントを抑えて取り組むことが大切です。
メインのキーワードを決める
まずは、サイトテーマもしくはカテゴリのトップとなるメインのキーワードを選びましょう。
基本的にメインのキーワードは、検索ボリュームの大きいキーワードとなることが多く、検索意図は抽象的になると思いますが、それでも問題ございません。
抽象的なキーワードから、階層が下のカテゴリになればなるほど具体的な検索意図のキーワードになるようカテゴリを設定していきましょう。
また、カテゴリを設定する際はサイトのテーマに関連したキーワードで設定してください。
そうすることでよりサイトの専門性が増し、検索エンジンに評価されやすいサイトとなります。
例えば弊社のサイトのカテゴリだと、親カテゴリ=「SEO」、子カテゴリ=「SEO 内部対策」「コンテンツSEO」「SEO 外部対策」のように設定しておりますので、参考にしてみてくださいね。
▼関連記事
カテゴリ名には対策キーワードを含める
これは当たり前のことではありますが、カテゴリ名にも上位化を狙うキーワードを設定しましょう。
そうすることで、そのキーワードでのカテゴリページの上位化を狙うことができます。
また、選ぶキーワードの目安としてはビッグキーワードからミドルキーワードを設定し、サイトのメインテーマに関連するキーワードを選ぶようにしましょう。
階層については上記でも記載しておりますが、カテゴリ名に使用するキーワードは検索ボリュームがある程度あり、検索意図も複数考えることができるようなキーワードを選ぶことをおすすめします。
そして、そのカテゴリに含める記事はカテゴリに関連し、検索意図がはっきりしているスモールキーワードを選ぶと、ユーザーにとってより分かりやすいサイト構造となります。
▼関連記事
自然な階層を意識する
こちらも上記でお伝え致した内容とはなりますが、カテゴリ階層は自然な階層を意識することが大切です。
親カテゴリやそれに追随する子カテゴリによってあまり不自然な順序で階層を作ることはおすすめしません。
あまりにも不自然になってしまうと、クローラーやユーザーの利便性が損なわれてしまいます。
自動車サイトを例に考えてみましょう。
例えば、冒頭で紹介した「自動車→SUV・軽自動車→メーカー・走行距離」という階層であれば、自然な流れとなり利用しやすいサイトです。
しかし、「自動車→メーカー・走行距離→軽自動車・SUV」というような、不自然な流れになると直感的な操作ができないためユーザーの利便性低下につながります。
またカテゴリが細かすぎたり階層が極端に深くなってしまった場合でもSEO評価が低下します。
カテゴリ階層はクリック3回でどのページにもアクセスできるのが理想的です。
そうすることで、サイトの利便性が向上しGoogleからの評価の向上に繋がる可能性があります。
また、クローラーがサイトを巡回する際に、サイト内のリンクを辿り巡回します。
ですので、ユーザーが3クリック以内にどのページにもアクセスできる階層にしておくことで、結果クローラーも巡回しやすいサイトとなり、コンテンツを適切に評価してもらえるサイトとなるのです。
内部リンクの充実
同じカテゴリの記事であれば、記事同士を内部リンクでつなげて内部リンクの充実を図ることも重要です。
内部リンクが充実していれば、サイトの利便性向上に繋がり、ユーザーのサイト内の回遊率が向上します。
また、利便性が向上しサイト内の回遊率がアップすれば、クローラーもサイト内を巡回しやすくなりSEO効果を高めることが可能です。
サイトが大規模になると内部リンクが途切れたりすることもあるでしょう。
しかし内部リンクが途切れたままだと、検索エンジンに認識されないカテゴリやコンテンツが生まれる可能性もあります。
クローラーやユーザーの回遊率も低下してしまい利便性も悪いため定期的に確認することが大切です。
▼関連記事
パンくずリストは忘れずに設定
パンくずリストとは、ページの上部にあるカテゴリの道順を表示している機能のことをいいます。
▼弊社のパンくずリスト

パンくずリストを設定することで、ユーザーが今サイトのどのページを閲覧しているのか、どの階層にいるのかを素早く判断することが可能です。
サイトにおける案内地図の役割を果たしているため、基本的には全てのページに設置しましょう。
▼関連記事
カテゴリ分けの注意点
次にカテゴリ分けの注意点について3つほど紹介します。
分類する階層が多いまたは少ない
「自然な階層を意識する」の項目でも簡単に触れていますが分類する階層を多くし過ぎないようにしましょう。
カテゴリが細かすぎるとユーザーにはかえって分かりにくく、利便性の低下につながるからです。
例えば、先程の自動車の例を使用すると「自動車→普通車→5人乗り→右ハンドル→ガソリン車→低燃費」などのように階層が多すぎると目的のページに辿り着きづらく、利便性の悪いサイトとなってしまいます。
しかしカテゴリが大雑把で階層が少なすぎるとこちらもユーザーは情報を見つけにくくなり、利便性の低下につながります。
例えば、「自動車→普通車・軽自動車」のみしかカテゴリがない場合、こちらも目的のページまで辿り着きづらく利便性が悪いサイトとなってしまいます。
多すぎず少なすぎず適度なバランスを保って、カテゴリ分けを行うことが大切です。
1記事につき1カテゴリにする
原則として、1記事1カテゴリで設定して、複数のカテゴリ設定はやめましょう。
記事の内容によってはカテゴリを複数設定したい場合もあると思います。(ただ、複数設置できるカテゴリがある場合はテーマが被っている可能性もありますので、カテゴリを1つにできないか確認しましょう。)
しかし1記事で複数のカテゴリを設定した場合、違うカテゴリから同じ記事にたどり着いたユーザーは「この記事は同じなのか違うものなのか」と混乱してしまいます。
例えば極端な例にはなりますが、カテゴリAとカテゴリBに含まれている記事が同じものばかりだと、サイトを訪れたユーザーに不信感を与えてしまう可能性もあります。
また複数のカテゴリに設定しても、パンくずリストには1つのカテゴリしか表示されません。
ですので、カテゴリを複数設定したからといって流入数が増えるようなことは起こらないのです。
そのため1記事に設定するカテゴリは1つにしましょう。
似た名前や種類のカテゴリ作成は厳禁
例えば、「自動車>軽自動車>軽トラック」というカテゴリが出てきたら、どのように感じるでしょうか。
軽トラックは軽自動車ジャンルの軽貨物車としての位置づけのためカテゴリ的には同じです。
そのため車に詳しい方は違和感を覚る可能性があります。
このように本来は同じであるテーマをカテゴリ分けしてしまうとユーザーの利便性はもちろん、信頼性も損なわれるためすぐに影響はなくとも長期的にみるとマイナスに作用します。
似た名前や似た種類のカテゴリの作成は避けて同じテーマのものは同一のカテゴリで統一することが大切です。
カテゴリあらかじめ設定しておくことが大切
SEOのカテゴリ分けについて概要とポイント、注意点を解説しました。
冒頭でも紹介した通り、カテゴリ分けはWeb構造そのものですので、利便性やSEOに直結します。
リリース後のカテゴリ変更はSEOにも影響するため、サイト設計時にしっかりとカテゴリ分けを行うことが大切です。
しかし、カテゴリに分類する記事が少ないとこれもSEOに直結するため、タイミングを見ながらしっかりと作りこむ必要があります。
カテゴリ分けとSEOとの関係性をしっかりと理解しておきましょう。
関連