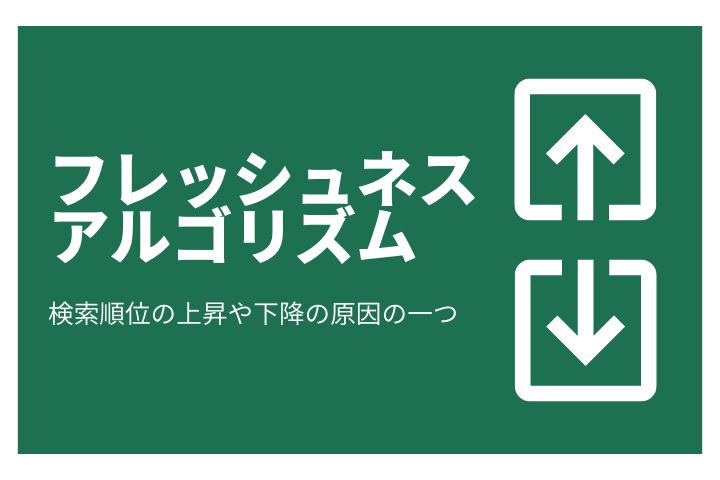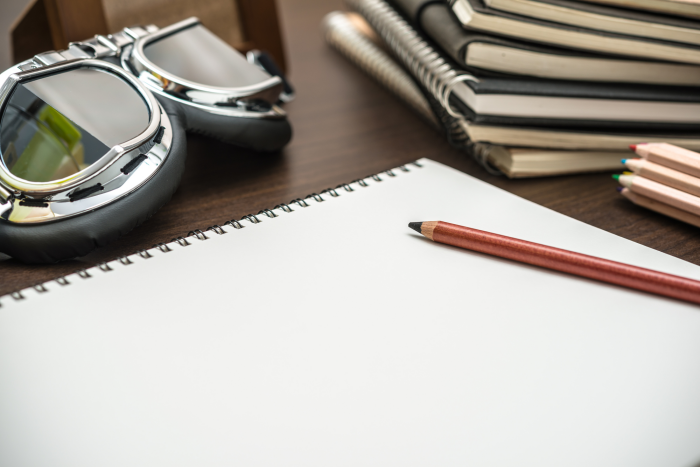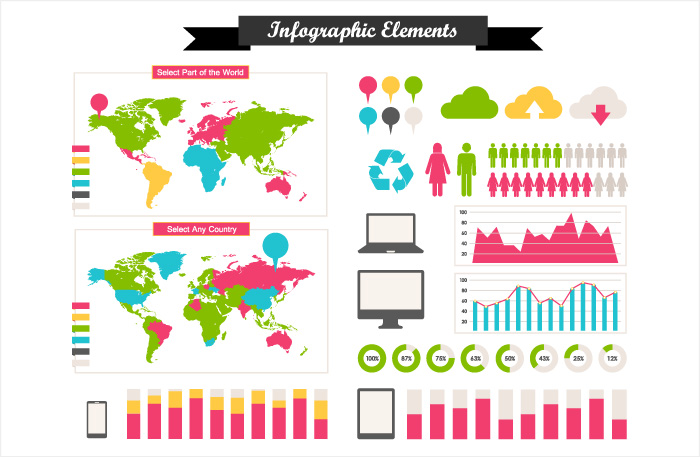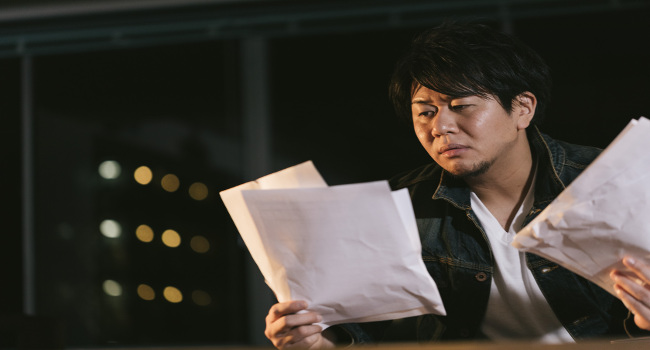フレッシュネスアルゴリズムとは?更新後の検索順位が上昇・下降する仕組み
2022.12.08
フレッシュネスアルゴリズムが更新後の検索順位に与える影響をご存知ですか?
中には、「古いので対策しても意味がないのでは?」「QDFと同じでしょ!」と誤解されている方も多いようです。
そこで今回は、影響を受けるサイトと受けないサイトの違い・Googleの評価基準・対策ポイントなどをご紹介します。
なぜ更新した記事の順位が上昇または下降するのか?
まず大前提として、検索順位は常に変動しているのが正常な状態です。
毎日、新しいコンテンツがWeb上に投稿されているのですから、どんなに優良なコンテンツでも検索上位をキープできる保証はありません。
ただし、コンテンツを更新してから一定期間を経て検索順位が上昇した、あるいは下降しているなら「フレッシュネスアルゴリズム」の影響を受けている可能性があります。
更新後に検索順位が変動する要因
- 検索順位が上昇した:修正、追記した内容が正確で鮮度が高い
- 検索順位が下降した:修正、追記した内容が間違っている、または情報が古くて鮮度が低い
フレッシュネスアルゴリズムとは?
フレッシュネスアルゴリズム(Freshness algorithm)とは、ユーザーがよりタイムリーな情報を素早く入手できるよう、「鮮度の高い最新情報を提供しているWebページ」を上位表示させる目的で2011年に導入されたGoogleのアルゴリズムです。
なぜフレッシュネスアルゴリズムアップデートが導入されたのか、その理由はGoogleには「検索キーワードに対して表示されるコンテンツが新しいほど、ユーザー体験(UX)が向上する」という理念があるからです。
関連記事
影響を受けるタイミングは?
フレッシュネスアルゴリズムは、下記のタイミングで検索ランキングが上昇または下降する傾向が見られます。
タイミングの一例
- 新規記事の追加
- 既存記事の更新
- ドメイン変更
- SSL化
フレッシュネスアルゴリズム対策は古くて通用しない?
結論から言うと、フレッシュネスアルゴリズム対策は2022年時点でも有効です。
「2011年に導入されてから10年以上も経っているのだから、影響は小さいのでは?」という印象をお持ちの方も多いでしょう。
しかし、ここ数年で世界的に蔓延した「コロナ」の影響もあり、むしろ近年の方が「最新情報」に対するニーズが高まっているのです。
中でも、YMYLやリアルタイムな情報が必要なトピックを扱うWebサイトでは、未だにフレッシュネス指標(アルゴリズム)を重要視する必要があります。
QDFアルゴリズムとの違いとは?
フレッシュネスアルゴリズムと混同されがちなのが、QDFアルゴリズム(Query Deserves Freshness)です。
2つのアルゴリズムには「トレンド性・話題性の高いコンテンツほど上位表示される」という共通点はあるものの、「対象キーワードの範囲」という決定的な違いがあります。
フレッシュネスアルゴリズムとQDFアルゴリズムの違い
- フレッシュネスアルゴリズム:「トレンド性」や「話題性」が求められる全てのキーワード
- QDFアルゴリズム:ニュースやSNSなどで一時的に検索ボリュームが増加した、特定のキーワード限定
特定のキーワードに限定されるQDFアルゴリズムは、芸能人のゴシップ記事や新商品をリリースした人気ブランドなど、いわゆる「トレンド入り」しているテーマが上位表示されるため、短期間で爆発的なアクセスが見込めます。
ただし、タイムリーな話題は刻々と入れ替わるため、その効果に持続性はありません。
「コンテンツ=資産」と捉えるなら、むしろ常に新しい情報が求められるフレッシュネスアルゴリズムを、あくまでSEO対策の一環として認識した方が良いでしょう。
フレッシュネスアルゴリズムの影響を受けるサイト
コロナ禍でフレッシュネスアルゴリズムが再注目されているのは事実ですが、だからと言って全てのWebサイトが影響を受ける訳ではありません。
Googleはフレッシュネスアルゴリズムの対象ジャンルを公開していませんが、長年ランキング変動を観察してきた経験から、実際に影響を受けているサイトの種類をご紹介します。
フレッシュネスアルゴリズムの影響を受けやすいサイト
- 最新ニュースや注目トピック:ゴシップ・選挙結果
- 定期的に開催される行事:イベント・スポーツ観戦
- 繰り返し更新が必要な情報:気象情報・防災情報
- YMYL:医療・金融
最新ニュースや注目トピック:ゴシップ・選挙結果
フレッシュネスアルゴリズムの影響を受ける代表例として、最新ニュースや注目トピックを扱っているコンテンツが挙げられます。
最新ニュースや注目トピックの一例
- 芸能人のゴシップ
- 衆院選や参院選など、大規模な選挙の結果速報
- 異質な犯罪事件
- 大規模事故
- 国際紛争
優先的に上位表示されるのは、全国シェアの大手新聞の一面で取り上げられている、あるいは数分~数時間前にWeb上に流れ始めた情報などです。
定期的に開催される行事:イベント・スポーツ観戦
イベントやスポーツ観戦の直近スケジュールなど、定期的に開催される行事に関する情報を扱っているWebサイトも、フレッシュネスアルゴリズムの影響を受けます。
定期的に開催される行事の一例
- オリンピックの競技スケジュール
- サッカーや野球の国際試合
- テニスの4大大会
- ゴルフのマスターズ・トーナメント
- 年末のカウントダウンライブ
- 夏フェスなどの野外ライブ
- 花火大会
直近のスケジュール情報だけでなく、結果速報を扱うコンテンツなども対象です。
繰り返し更新が必要な情報:気象情報・防災情報
下記のようなトピックは常に最新の情報へと更新する必要があるため、たとえ同じキーワードを扱っていても鮮度の高いコンテンツの方が優先的に上位表示されます。
繰り返し更新が必要な情報の一例
- 気象情報
- 災害情報
- 地震情報
- 避難所の設置場所
- 休日の当番病院
- 高速の渋滞情報
- ホリデーシーズンの新幹線の予約率
- 商品のリコール情報
- 最新機種のリリース情報
YMYL:医療・金融
YMYL(Your Money Your Life)にカテゴライズされているWebサイトは、その性質上フレッシュネスアルゴリズムの影響を特に受けやすく、順位変動のふり幅も大きい傾向が見られます。
GoogleがYMYLに対して年々ルールを厳格化しているのは、「人の生命・金融・幸福などに関する情報」だからです。
つまり、厳密に言うと下記の一例に加えて上記でご紹介した災害情報や選挙の結果速報なども、Googleが注視しているYMYLに当たります。
YMYLなど
- ワクチン接種が可能な病院の情報
- コロナの感染者数
- 訪問医療の案内
- FX(為替レート)
- 株価の変更情報
専門性と信憑性が問われるジャンルですから、最も上位表示されやすいのは有資格者が実名で提供している情報です。
素人がWebサイトを運営している場合は、プロに監修を依頼することで優遇されることもあります。
関連記事
フレッシュネスアルゴリズムの影響を受けないサイト
フレッシュネスアルゴリズムは、話題性の高いテーマやタイムリーな情報が求められるキーワードを扱うコンテンツのみに影響するのが特徴です。
言い換えれば、下記のように「ほぼ正解が決まっているジャンル」や「普遍的なテーマ」を扱っているサイトは、フレッシュネスアルゴリズムの影響を受けません。
影響を受けないサイト
- 用語解説
- 歴史上の人物紹介
- 世界的な宗教の解説
- 定番メニューのレシピ
むしろ、数年前に問題になった「まとめ」サイトのように、事実とは事なる奇をてらったフェイクニュース的な記事を最新情報と偽って掲載すると、Googleのガイドラインに抵触して検索結果が下落したり表示されなくなったりします。
フレッシュネスアルゴリズムの適用外要素
結論から言うと、フレッシュネスアルゴリズムの評価対象は見出しと本文で構成されている「メインコンテンツ」だけに限定されています。
確かに、芸能ニュースやイベント情報を提供しているコンテンツはフレッシュネスアルゴリズムの影響を受けますが、だからと言ってサイト内の全要素が評価対象という訳ではないのです。
更新や変更を行っても記事内容の鮮度に大きな影響を与えない下記の要素は、フレッシュネスアルゴリズムの評価対象ではありません。
フレッシュネスアルゴリズムが適用されない要素
- ヘッダー
- フッター
- サイドバー
- コメント
- タイムスタンプ(記事の公開日・最終更新日)
- 広告
- HTML・CSSの変更
- UGC(クチコミサイトなどのユーザー生成コンテンツ)
Googleの評価ポイント
「単語を置き換える」または「タイムスタンプを変更する」といった小手先のSEOテクニックは、フレッシュネスアルゴリズムに通用しません。
むしろ、意図的に鮮度を偽装していると見なされて、検索順位が下降してしまうケースもあるのです。
更新に向けて記事をリライトする場合は、下記の4つの評価ポイントに注力しましょう。
評価されるポイント
- HTMLの変化量
- キャッシュの更新頻度
- 被リンクの獲得頻度
- ソーシャルシェアの頻度
HTMLの変化量
1つ目の評価ポイントであるHTMLの変化量とは、ページのbodyに当たるメインコンテンツのボリュームを指しています。
なぜHTMLの変化量がフレッシュネスアルゴリズムの評価ポイントなのか、その理由は検索エンジンが更新の程度を判断する基準にしているからです。
クローラーの判断基準
- HTMLの構造変化が大きい→大幅に更新されている
- HTMLの構造変化が小さい→更新された内容が少ない
つまり、たとえ開催日時などの単語だけを入れ替えてもコンテンツ全体のボリュームが変わっていなければ、「見せかけの更新」と見なされてしまうのです。
イベントの開催日時が変更になった場合は、日付だけでなく理由やチケット返金の案内といった補足情報も併せて記載し、HTMLの変化量を顕著にしておきましょう。
キャッシュの更新頻度
Googleのクローラーは、ネット上をクローリングしながら膨大な情報を迅速に処理するためにキャッシュ(情報を一時的に保存する機能)を使っており、サイトを巡回する度にキャッシュ情報を更新しています。
しかし、更新する前の旧データが残っていると、Webページの最新情報を取得しようとしているクローラーの働きを阻害しかねなません。
クローラーが常に最新の更新情報を正確に収集できるよう、自身のPCやサーバーに残っているWebサイトのキャッシュを頻繁に更新しておきましょう。
ちなみに、お気に入りに登録しておいたページが直ぐに閲覧できるのは、このキャッシュの効果によるものです。
被リンクの獲得頻度
フレッシュネスアルゴリズムの評価ポイントとして、被リンクの獲得頻度も重要なファクターです。
ただし、一般的なSEO対策とフレッシュネスアルゴリズム対策とでは、評価基準が異なっています。
被リンクに対する評価基準の違い
- 一般的なSEO対策:被リンクの「数」と「質」が重要
- フレッシュネスアルゴリズム対策:全体の量ではなく、「直近の獲得頻度」が重要
ソーシャルシェアの頻度
TwitterやInstagramといったソーシャルメディア上で、自身が提供している情報がより多く拡散されているほど、フレッシュネスアルゴリズム対策としてポジティブな効果が得られます。
傾向として、公開または更新してから短時間で大量のシェアを獲得したページが、ランキングの上位を占めているようです。
フレッシュネスアルゴリズムのSEO対策ポイント
コロナの影響でフレッシュネスアルゴリズムの注目度が高まっているからと言って、アルゴリズム対策だけに頼るのはおすすめできません。
ここからは、通常のSEO対策とフレッシュネスアルゴリズム対策の両方にとって有効な、3つのポイントをご紹介しましょう。
対策のポイント
- 評価されるのはメインコンテンツのみ!
- 上位表示されるのは高低品コンテンツだけ!
- 更新頻度が多いほど有利!
評価されるのはメインコンテンツのみ!
前述した通り、ページのbodyに当たるメインコンテンツだけを評価対象として限定しているのがフレッシュネスアルゴリズムの特徴です。
したがって、記事の内容をほとんど変えずに最終更新日だけを変更する、見た目が変化するCSSだけに手を加える、といった手法で更新頻度ばかりを稼いでも全く効果はありません。
フレッシュネスアルゴリズムを攻略して検索順位の向上を目指すなら、あくまでメインコンテンツの内容と量的変化に重点をおいてリライトを行いましょう。
関連記事
上位表示されるのは高品質コンテンツだけ!
どんなに注目されている話題を提供していようと、コンテンツの品質が低ければランキング上位に表示されることはありません。
稀に炎上商法などで瞬間的にランクアップするケースもありますが、内容に虚偽の情報が含まれていたり記事そのものが稚拙だったりすると、短時間で圏外にドロップアウトしかねないのです。
最悪の場合、インデックスが外されて検索結果から消える、またはGoogleからペナルティを受ける可能性もあります。
Googleが公言している通り、まずはE-A-Tが担保されている「高品質なコンテンツ作り」に努めるのが先決です。
関連記事
更新頻度が多いほど有利!
更新頻度を増やしてもSEOに直接影響することはありませんが、間接的な効果は見込めます。
そもそも、フレッシュネスアルゴリズム対策としてタイムリーな情報を書き足しても、更新後にGoogleクローラーが巡回してくれなければ検索結果に反映されません。
その点、更新頻度を増やせばクロールされる機会も増えますので、その分ランキングアップの可能性が高まります。
まとめ
ここ数年でフレッシュネスアルゴリズムに対する関心が再熱しているため、時事ニュースやトレンドネタを扱うサイトも増えているようです。
ただし、ニーズの高いジャンルだからこそ競争率が高く、何とか大手に対抗しようと強引な手法を取り入れているWebサイトも見かけます。
特に、フェイクニュースを取り上げている記事は一時的にアクセス数が急上昇するものの、その後は急激に低下するだけでなくサイト自体の信用も失い兼ねません。
検索順位を上げるにはアルゴリズム対策だけでなく、「有益で上質なコンテンツ」を生み出すことを意識しましょう。
関連