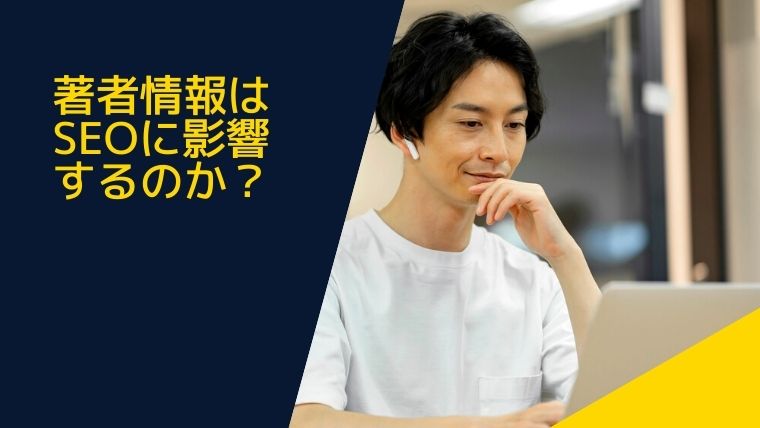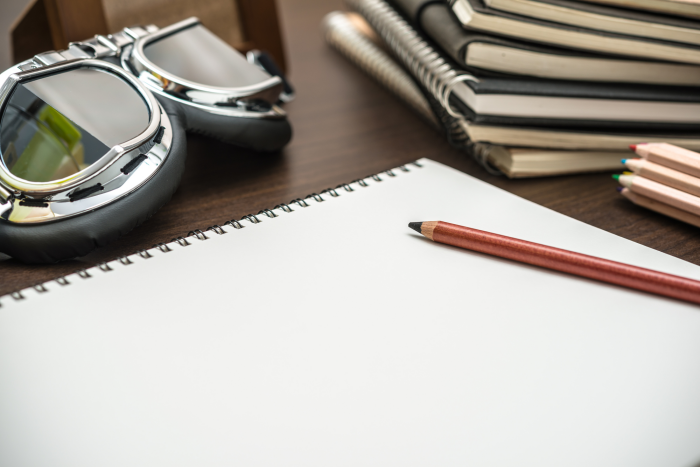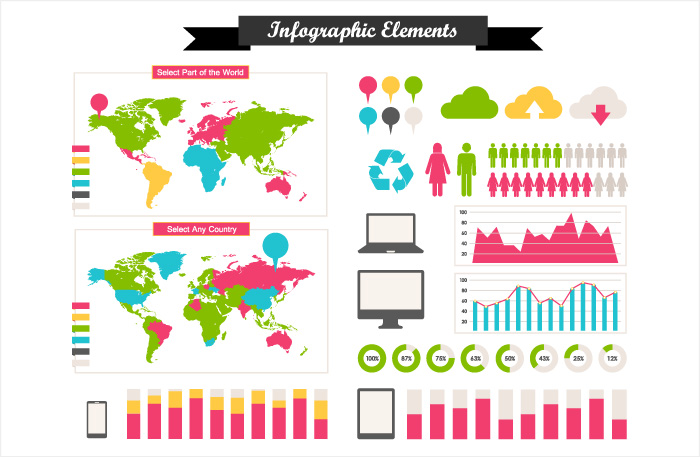著者情報はSEOに影響するのか?Googleの評価方法と記述例
2021.05.31
著者情報を記載すると検索順位は上がるか?と疑問に思っている方も多いでしょう。そこで本記事ではプロフィールなどの著者情報を記載するとSEOにどのような影響を与えるのかまとめてみました。コピペOKの記述例も合わせてご紹介します。
著者情報の記載はSEOに効果があるのか? 結論から言うと、自サイトに著者情報を記載する行為はSEOにポジティブな影響を与えます。
その根拠として挙げられるのが、Googleが2018年に公開した「検索品質評価ガイドライン」に記載されているE-A-Tに関する一文です。
ページを評価するには、Webサイト及びメインコンテンツ制作者の「評判」「専門性」「権威性」「信頼性」を考慮する必要がある。
引用:General Guidelines
言い換えれば、下記5つの疑問に対して明確に回答できている著者情報ほどユーザーに安心感を与え、SEOにポジティブに影響する分だけ検索順位も上がる仕組みになっているのです。
▼著者情報のポイント
誰がコンテンツを書いたのか?
筆者はユーザーや同業者から信頼されているか?
筆者はこの分野の専門家なのか?
この記事に書かれている情報は信用できるのか?
この記事の責任者は誰なのか?
特にGoogleは、お金・健康・法律に関する情報をメインテーマにしているYMYLサイトに対してE-A-Tを重視しているため、著者情報の記載が効果的なSEO対策となります。
9.2 Reputation and E-A-T: Website or the Creators of the Main Content?
You must consider the reputation and E-A-T of both the website and the creators of the MC in order to assign a Page Quality rating.
The reputation and E-A-T of the creators of the MC is extremely important when a website has different authors or content creators on different pages. This is true of forum and Q&A pages, news websites, or websites that have user-generated content, such as YouTube, Twitter, etc. The reputation and E-A-T assessment for pages on these types of websites may differ drastically depending on what page you are evaluating. There are Highest quality YouTube videos created by highly reputable and expert content creators, as well as Lowest quality YouTube videos created with a dangerous lack of E-A-T on YMYL topics.
引用:General Guidelines
なお、E-A-T やYMYLについては下記の記事をご一読下さい。
Googleは著者情報のアルゴリズム導入に失敗していた! これまでGoogleは、著者情報を検索アルゴリズムに用いる方法を模索してきました。
その目的を大きく分類すると、下記の2種類に分けられます。
▼検索アルゴリズムに著者情報を導入する目的
検索結果の上位に、より優れた著者のコンテンツを表示させるため
コピーコンテンツかオリジナルコンテンツかを見極めるため
この試みは、何度か失敗に終わったものの、数年後に再び著者情報が重要視されるようになり、SEO対策のスタンダードとして扱われるようになったのです。
まずは、これまでの失敗例から見ていきましょう。
オーサーシッププロジェクトと著者情報の関係 Googleは、より優れた著者の記事をランキング上位に表示させるべく、2011年にオーサーシッププロジェクト を開始しています。
しかし、下記の動画でジョン・ミューラー氏(John Mueller)が言及している通り、検索アルゴリズムに著者情報を導入する試みは2016年時点でほぼ失敗していると認めているのです。
VIDEO
上記の動画を要約すると、注目すべき3つのポイントが分かります。
▼著者情報とSEOの関係性について
現時点でGoogleは、誰が書いた記事なのか把握できていない しかし、投稿履歴を遡って筆者を推定することは可能
コピーコンテンツよりオリジナルコンテンツを上位化する試みを続けている
google+(グーグルプラス)と著者情報の関係 もう一つの失敗例として挙げられるのが、2011年からスタートしたSNSの一種である「google+」です。
たとえWebサイトに著者情報が記載されていなくても、系列のSNSを紐づけることでコンテンツの筆者や責任者を簡単に突き止めることができます。
▼google+で著者情報が明らかになる仕組み
「rel=”author”」を用い、WebサイトからGoogle+へリンクを張る
クローラーにGoogle+の情報が伝わり、筆者または責任者が同一だと認知される
そのため、Webサイトの運営者が集うSEOフォーラムでは「記名を義務づけているFacebookに対抗しているのでは?」という話題が沸騰していました。
ところが、2014年にgoogle+の著者情報プログラムが終了したのに続き、2019年4月にはgoogle+自体が完全に廃止されてしまったのです。
Googleは著者情報を認識できる!推奨している方法2つ 過去の失敗例を根拠に、一時は「著者情報とSEOに関係性はない」という意見が優勢でした。
しかし、2018年に発信されたジョン・ミューラー氏(John Mueller)からのアナウンスを受け、著者情報がSEO対策の一環として再び注目されるようになったのです。
VIDEO
ジョン・ミューラー氏は上記の動画でGoogle+に代わる著者情報のSEO対策について言及しており、2通りの方法を推奨しています。
▼Googleが推奨する著者情報の取り扱い方
「構造化データ」で著者情報をマークアップする
Webサイトに、筆者または責任者の「プロフィールページ」を設ける
上記のいずれかを講じることで、Google は「誰のコンテンツなのか」が認識できるようになるのです。
プロフィールページの著者情報はSEO効果が低いのか? 外部からの評価が優先されるからと言って、プロフィールページに載せる著者情報のSEO効果が低いという訳ではありません。
サイトにプロフィールページを設けることで、下記のようなメリットが得られます。
▼プロフィールページを設けるメリット
対ユーザー:著者情報を探し回る必要がない分、信頼されやすい
対クローラー:比較する元情報が直に伝わる分、外部の評判も見つけやすい
つまり、プロフィールページに著者情報を記載すること自体が、効果的なSEO対策になる のです。
Googleは著者情報の評価にスコアをつけているのか? 結論から言うと、Googleは著者情報を評価する際にスコアをつけているとは明言していません。
ただし、2018年度版の検索品質評価ガイドライン(2.6の章) には、著者情報の評価は「外部からの著者評判を優先する」と記載されています。
自サイトに掲載するプロフィールは、いくらでも改ざんが可能です。
これに対し、他サイトからの評価は改ざんリスクが低いため、より公平なSEO要因として作用します。
著者情報に含めるべき情報とは? この段落では、著者情報に含めるべき具体的な情報を、2種類のカテゴリに分けて解説します。
▼著者情報のカテゴリ
プロフィール・記事内に記述すべ著者情報
メタデータに記述すべき著者情報
プロフィール・記事内に記述すべ著者情報 プロフィールに載せる著者情報は少なくとも下記4項目を記述し、全てのページからアクセスできるようにしておきましょう。
記事の本文に、「この記事を書いた人」と記載してプロフィールページに誘導するのも有効な手段です。
▼プロフィールや記事内に記述すべ著者情報
略歴:職歴/本職(副業の場合)/なぜサイト内容の知識が深いのか
サイトの解説:どのような情報を、何を目的に発信しているのか
ライターとしての経歴:これまで執筆してきたコンテンツの分野や記事数
スキル:保有資格/著名なサイトからの外部リンク数など
プロフィールはGoogleのクローラー向けというよりも、ユーザーに向けて分かりやすい言葉で記載するのがポイント。
「記事の内容を信じて良いのか?」と疑っているユーザーに対し、信憑性の裏づけとなる内容が理想的です。
メタデータに記述すべき著者情報 メタデータにマークアップする著者情報は、下記6項目が基本となります。
▼メタデータに記述すべき著者情報
Headline:記事タイトル
DatePublished:記事の公開日
DateModified:記事の更新日
Author:著者名(本名が理想的)
Image:アイキャッチ画像(証明写真のような実写が理想的)
Publisher:運営元の組織情報(法人名やサイト名)
WordPress(ワードプレス)を使用されている方は、ご利用のテーマに「カスタムJavaScript設定」が付加されているか確認してみましょう。
手動で記述するよりも簡単に著者情報をマークアップすることが可能です。
SEOに強い著者情報の記述方法3つ 最後に、著者情報を記述する3つの方法についてテンプレートつきで解説します。
それぞれテンプレートを記載していますので、自サイトの情報に書き換えてご利用ください。
▼著者情報を記述する方法
構造化マークアップ
HTMLのauthorタグ
ページタイトルの後半に著者名を追加する
構造化マークアップ プロフィールページは、Googleが推奨している「JSON-LDの構造化マークアップ」が最適です。
下記のテンプレートは、上記の「メタデータに記述すべき著者情報」でご紹介した項目を満たしています。
<script type="application/ld+json">{
"@context" : "http://schema.org",
"@type" : "Article",
"headline" : "記事タイトル",
"datePublished" : "記事の公開日2021-5-31",
"dateModified" : "記事の更新日2021-6-1",
"mainEntityOfPage" : "記事のURL https://pecopla.net/seo-column/author-information-seo",
"author" : {
"@type" : "Person",
"name" : "著者名 ぺコプラ太郎"
},
"image" : {
"@type" : "ImageObject",
"url" : "https://pecopla.net/images/pecopla.jpg",
"width" : "1920",
"height" : "1088"
},
"publisher" : {
"@type" : "Organization",
"name" : "運営元の組織情報 株式会社ぺコプラ",
}
}</script>
HTMLのauthorタグ metaタグのhead内に下記のように記述すると、Googleに正確な著者情報が伝わります。
<meta name="author" content="ぺコプラ太郎">
ただし、上記だけでは記事内に表示されないため、ユーザー向けにサイト内にプロフィールページを設けたうえで、下記のようにリンクさせましょう。
<a rel="author" href="プロフィールページ" >著者:ぺコプラ太郎<a>
ちなみに、htmlの知識に自信がないという方はワードプレスのプラグイン「Simple Author Plugin」が便利です。
ページタイトルの後半に著者名を追加する Googleで検索した際、記事タイトルの最後にサイト名や著者名が表示されていると、「誰が提供している情報なのか」が一目でユーザーに伝わります。
下記の通り記述方法がとても簡単なので、別途サイト内にプロフィールページも設けておきましょう
<title>記事タイトル/ぺコプラ太郎</title>
まとめ 著者情報の開示はユーザーの信頼を得るための重要なツールであり、SEOにもポジティブな影響を与えます。
関連