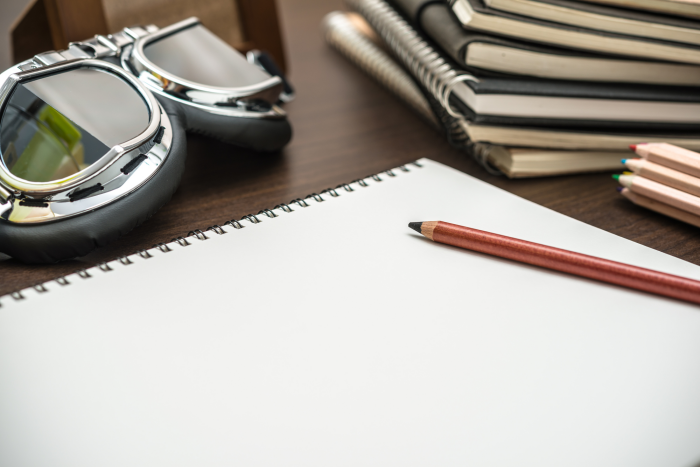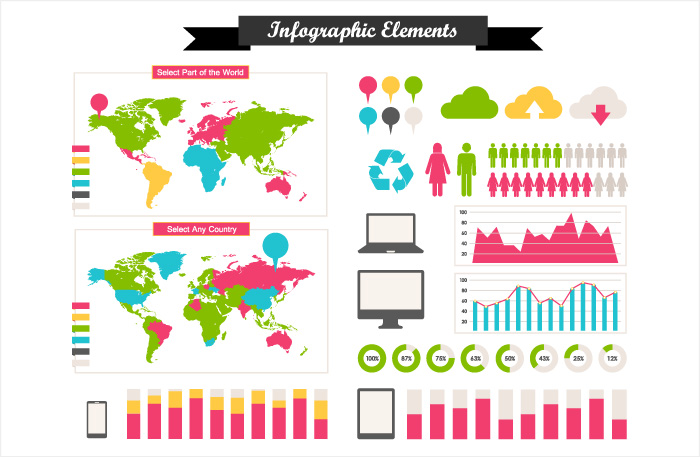【SEOの基本】インデックスとは?順位への影響や促進方法を紹介します
2024.09.19
インデックスされることにより、はじめてGoogleにウェブページが認識されます。Googleにウェブページが認識されなければ、検索結果に表示されず、アクセスが増えることはありません。SEO対策を行ううえで非常に重要なインデックスについて解説します。
インデックスとSEOの関係とは?
インデックスは、Web制作者にとって「SEOの大前提」「SEOの第一歩」と例えられる存在です。なぜインデックスはそれほどまでにSEOにとって重要なのでしょうか?
インデックスとは?
インデックスとは、Googleクローラー(ウェブページを巡回し情報を収集してデータベースに登録するプログラム)がWebページを認識し、データベースに登録することを指します。
たとえWebサイトを公開してもインデックスされるまではGoogleはウェブページを認識していないため、検索結果ページに表示されません。
通常、ウェブページの新規作成や既存ページの更新を行うと、一定期間の後にGoogleクローラーがインデックスしてくれます。
ただし、「更新頻度が低い」または「内部リンクが少ない」などクローラーが巡回しにくいWebサイトの場合、インデックスが遅れることが多いようです。
インデックスから検索順位が決まるまでの仕組み
クローラーは、アンカーテキストをはじめとする他ページに設置された「リンク」や所有者から通知された「サイトマップ」などを元にWebサイトに辿り着き、下記のようなプロセスを経て検索順位を決定します。
▼クローラーの働き
- Webサイト内をクロール(巡回)し、データを収集する
- インデクサプログラムによって収集したデータを検索しやすい状態に処理して登録する
- ユーザーの検索ワードとインデックスしたデータをマッチングする
- 検索ワードに対し関連性と評価の両方が高いコンテンツから上位に表示させる
つまり、Googleのクローラーにインデックスされなければ検索表示の順位を競うランキングにエントリーすらされないばかりか、他に講じたSEO対策の全てがムダになってしまうのです。
ちなみに、GoogleクローラーへWebページの存在を伝えるアンカーテキストリンクの最適化については、下記の記事を参考にして下さい。
▼関連記事
インデックス数は検索順位に影響する?
作成したWebページをインデックスさせることはSEOにおいて非常に重要ですが、インデックス数を増やすことを目的にWebページを作成するのは正しいのでしょうか。
「インデックスの数」より「コンテンツの質」が重要
結論から言うと、高品質コンテンツのインデックス数を増やすことはSEO効果の向上に役立ちますが、反対に低品質コンテンツのインデックス数ばかりが増えると評価を下げる要因になってしまいます。
特に、Googleがパンダアップデートを導入して以降はコンテンツの「数」より「質」が重視されるようになり、ユーザーファーストやコンテンツファーストといった考え方がSEOの主流となりました。
そのため、近年では低品質コンテンツによって意図的にインデックス数を増やしている大規模サイトより、質の高いコンテンツだけを扱っている小規模サイトの方が高く評価される傾向にあります。
また、パンダアップデートの内容や導入後のSEO対策については下記の記事で詳しく解説しています。
▼関連記事
Googleがインデックス数について言及
Googleスパム対策チームのリーダーとして知られるマット・カッツ(Matt Cutts)氏は、「インデックスが多ければ検索順位が有利になるのか?」という疑問について明解な回答を発信しています。
ここでは、Googleが公開している下記の動画を要約しつつ特筆すべきポイントをピックアップしてみました。
- インデックス数が多いからといって検索順位は自動的に上がらない
- 闇雲にページ数を増やすだけでは、サイトの評価も検索順位も向上しない
- ただし、良質なコンテンツが多ければ各ページにリンクが集まりページランクも上がる
- ランキング付けされる機会を増やしたいなら「ロングテールSEO」が効果的
「ロングテールSEO」とは、統一されたテーマに基づいて異なる検索キーワードを使った良質コンテンツを増やす手法を指しています。異る検索クエリごとに集客が見込めるため、まずは質の高いコンテンツを作成したうえでインデックス数を増やすべきでしょう。
大量のページはまとめて公開?それとも段階的?
大量のページを一度に公開しても問題なくインデックスされるのか、この疑問についてGoogleのMatt Cutts氏は「20万ページをニュースアーカイブへ公開するケース」を例に挙げて解説しています。
こちらも、Googleが公開している動画の内容を要約しつつ注目すべきポイントをご紹介しましょう。
- Googleには20万ページを問題なくインデックスできる技術がある
- ただし、検索結果に突然大量のページが表示された場合はマニュアルウェブスパムチームのチェック対象になる
- チェック対象になっても、質が高ければ数十万ページの順位が落ちるのは稀
- とはいえ、タイミングに支障がなければ段階的に公開する方が望ましい
上記の情報から、大量のページを一度に公開しても問題なくインデックスされるが、段階的に公開するよりも時間がかかると解釈できます。
ページのインデックスを早める4つの方法
一定時間が経てば、ウェブページは自動的にインデックスされますが、次の方法を利用することで、インデックスを早めることが可能です。
URL検査(Fetch as Google)
URL検査はインデックスを行なっているGoogleクローラーに、特定のウェブページもしくはウェブページの直接リンクを巡回するように要請することができる機能です。以前は「Fetch as Google」という名称でしたが、現在では「URL検索」と名前が変更されています。
URL検査を利用することで、新規作成した記事を条件によって5分以内にインデックスさせることも可能です。しかし使用回数に制限があり、クローラーが巡回したウェブページが必ずインデックスされるわけではないので、注意しましょう。
sitemap.xml(サイトマップXML)
sitemap.xmlはサイトを構成するウェブページのURLや最終更新日などの要素をXMLタグでマークアップすることで、Googleにサイトのコンテンツの構成を伝えるファイルです。
sitemap.xmlを作成し、Search Consoleに登録しておくことで、効率的にクローラーがサイトを巡回することを可能にします。
▼関連記事
サイトのウェブページの更新情報を配信するための技術であるRSSフィードも、インデックスを促進するのに有効です。RSSフィードは最近更新されたURLのみが登録され、検索エンジンのダウンロードがsitemap.xmlよりも高頻度のため、sitemap.xmlと併せて利用しましょう。
内部リンクの整備
内部リンクを整備することで、より効率的にクローラーにサイト内のウェブページを巡回させることが可能です。クローラーはウェブページのリンクを辿りながらウェブページを巡回しています。そこで各ウェブページが内部リンクで繋がった状態にしておくことで、クローラーに内部リンクを辿らせ、一度に複数のウェブページをクローラーに巡回させることが可能です。
▼関連記事
まとめ
パンダアップデートによりコンテンツの質が重視されるようになったため、質の低いコンテンツでインデックス数を増やしても意味を成さなくなりましたが、高品質なウェブページが多くインデックスされているサイトは検索エンジンからの評価が高いです。
日頃から内部リンクでクローラーが巡回しやすいサイトにすると同時に、sitemap.xmlやRSSフィードなどを利用して、インデックスを促進しましょう。
関連