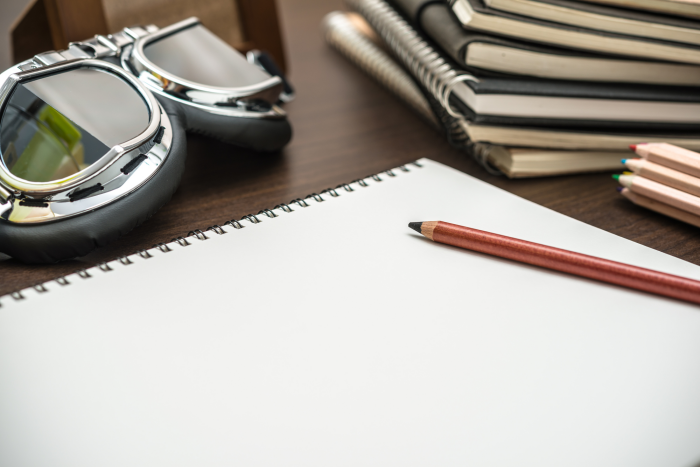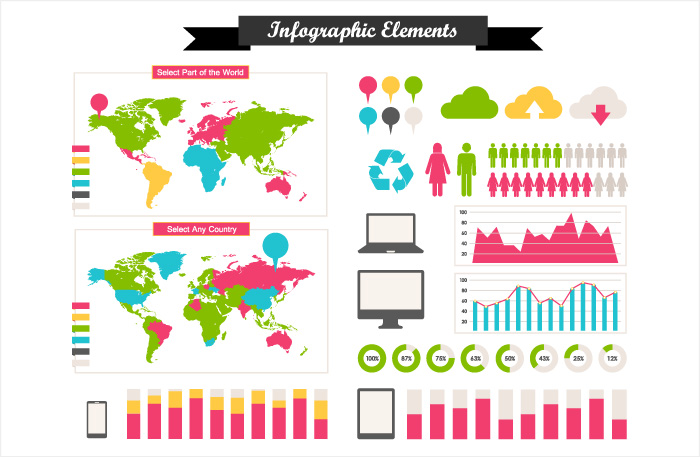SEOの基礎!クリック率とは?検索順位別クリック率と改善方法
2020.07.14
クリック率とは、サイトが表示された回数に対して、どれくらいの割合のユーザーがクリックしてくれたか、という指標のことです。「Click Throgh Rate」の頭文字を取って、「CTR」と呼ばれることもあります。
検索上位に表示することができても、クリック率が低ければアクセスを稼ぐことはできないため、クリック率は非常に重要です。このページではクリック率の計算方法と検索順位別のクリック率、クリック率の改善方法を紹介していきます。
SEOの基礎のクリック率とは
SEOにおいてクリック率は、コンテンツが表示された回数に対して、どれくらいの割合でユーザーにクリックされたかを示す指標です。たとえばコンテンツが100回表示されたうち、30回クリックされれば、クリック率は30%となります。
また検索順位別の平均クリック率を利用して、獲得できるアクセス数を予想することも可能です。たとえば検索ボリュームが1万の検索キーワードに対して、検索順位が2番目であれば、2位の平均クリック率が15%のことから1,500程度のアクセスが見込めます。
検索ボリュームについては下記の記事で解説しています。
掲載順位とクリック率の関係
クリック率は検索結果に掲載される順位によって大きく異なるものです。そこでここでは確認できた6年分の検索順位とクリック率を紹介します。
2020年4月の検索順位別クリック率
2020年4月の検索順位別クリック率は、以下の通りです。
| 検索順位 |
クリック率(PC) |
(スマホ) |
| 1位 |
32.4% |
26.9% |
| 2位 |
16.4% |
15.1% |
| 3位 |
10.4% |
10.1% |
| 4位 |
7.7% |
6.7% |
| 5位 |
9.0% |
4.7% |
| 6位 |
4.5% |
3.4% |
| 7位 |
3.0% |
2.5% |
| 8位 |
2.2% |
1.9% |
| 9位 |
1.7% |
1.5% |
| 10位 |
1.3% |
1.3% |
Advanced WEB RANKING
2019年4月の検索順位別クリック率
2019年4月の検索順位別クリック率は、以下の通りです。
| 検索順位 |
クリック率(PC) |
(スマホ) |
| 1位 |
31.19% |
22.44% |
| 2位 |
15.91% |
14.06% |
| 3位 |
10.07% |
9.27% |
| 4位 |
6.32% |
6.09% |
| 5位 |
4.28% |
4.17% |
| 6位 |
3.03% |
2.87% |
| 7位 |
2.19% |
2.08% |
| 8位 |
1.71% |
1.67% |
| 9位 |
1.38% |
1.31% |
| 10位 |
1.12% |
1.01% |
Advanced WEB RANKING
PC版の検索順位の1位から3位のクリック率は、1位が2位の2倍、3位の3倍になっています。検索上位の中でも1位を取れた時の恩恵は非常に大きいです。一方スマホ版でも検索順位1位が最もクリック率が高いことには変わりありませんが、検索上位5位までのクリック率のばらつきが小さいことがわかります。このことからPC版で1位の方がスマホ版で1位よりも価値が高いと言えそうです。
2018年4月の検索順位別クリック率
2018年4月の検索順位別クリック率は、以下の通りです。なお2019年との比較のため、クリック率の欄のカッコ内に2019年4月のデータも記載しています。
| 検索順位 |
クリック率(PC) |
クリック率(スマホ) |
| 1位 |
28.58%(31.19%) |
22.02%(22.44%) |
| 2位 |
14.19%(15.91%) |
13.83%(14.06%) |
| 3位 |
10.14%(10.07%) |
10.23%(9.27%) |
| 4位 |
6.27%(6.32%) |
6.46%(6.09%) |
| 5位 |
4.26%(4.28%) |
4.29%(4.17%) |
| 6位 |
3.01%(3.03%) |
2.99%(2.87%) |
| 7位 |
2.26%(2.19%) |
2.15%(2.08%) |
| 8位 |
1.78%(1.71%) |
1.59%(1.67%) |
| 9位 |
1.45%(1.38%) |
1.16%(1.31%) |
| 10位 |
1.15%(1.12%) |
0.84%(1.01%) |
Advanced WEB RANKING
2018年4月と2019年4月の検索順位別のクリック率を比較しても大きな違いはないことがわかります。このことから2018年4月から2019年4月にかけてPC版とスマートフォン版の検索順位とクリック率の傾向に変化はなかったと言えます。
2017年4月の検索順位別クリック率
2017年4月の検索順位別クリック率は、以下の通りです。なおカッコ内には2018年4月のデータを記載しています。
| 検索順位 |
クリック率(PC) |
クリック率(スマホ) |
| 1位 |
28.9%(28.58%) |
23.7%(22.02%) |
| 2位 |
14.3%(14.19%) |
15.02%(13.83%) |
| 3位 |
10%(10.14%) |
10.9%(10.23%) |
| 4位 |
6.47%(6.27%) |
7.21%(6.46%) |
| 5位 |
4.58%(4.26%) |
5.07%(4.29%) |
| 6位 |
3.29%(3.01%) |
3.63%(2.99%) |
| 7位 |
2.43%(2.26%) |
2.67%(2.15%) |
| 8位 |
1.87%(1.78%) |
2%(1.59%) |
| 9位 |
1.41%(1.45%) |
1.47%(1.16%) |
| 10位 |
1.06%(1.15%) |
1.06%(0.84%) |
Advanced WEB RANKING
カッコ内のクリック率を見てみると、2017年4月から2018年4月までの1年間でも大きな傾向の変化がないことがわかります。
2014年の検索順位別クリック率
2014年7月の検索順位別のクリック率は以下の通りです。なおカッコ内には2019年4月のデータを記載しています。なお6位以降はまとめての記載になっているため注意してください。
| 検索順位 |
クリック率(PC) |
クリック率(スマホ) |
| 1位 |
25.1%(31.19%) |
32.54%(22.44%) |
| 2位 |
10.02%(15.91%) |
15.98%(14.06%) |
| 3位 |
7.9%(10.07%) |
10.89%(9.27%) |
| 4位 |
4.89%(6.32%) |
7.69%(6.09%) |
| 5位 |
4.49%(4.28%) |
5.7%(4.17%) |
| 6位-10位 |
2.82% |
3.84% |
| 2ページ目 |
2.23% |
5.04% |
| 3ページ目 |
0.73% |
2.9% |
Advanced WEB RANKING
2019年4月と2017年7月検索順位別のクリック率を比較すると、スマートフォン版のクリック率が、2014年7月の段階では検索順位1位のページに大きく集中していたことがわかります。スマートフォン版の検索順位1のページは、2位の2倍、3位の3倍のクリック率を集めており、2019年現在のPC版に似た値となっています。このことから2014年から2019年にかけて、検索順位別のクリック率のばらつきが大きくなり、2位や3位のページでもアクセスを稼ぎやすくなったと言えそうです。
スマホ版のクリック率のばらつきが大きくなった理由
2014年から2019年にかけて、スマホ版の検索順位別のクリック率のばらつきが大きくなり、PC版の検索順位別のクリック率に近くなったのは、ユーザーが多くの情報をスマホで検索するようになったからだと考えられます。
以前のユーザーは、簡単な情報を手軽に調べる目的でスマートフォンを利用して検索エンジンを利用する傾向がありました。そのため検索結果のうち、検索順位が1位のページで簡単に情報を入手して、他のページは閲覧しなかったため、検索順位1位のページのクリック率が圧倒的に高かったのだと推測できます。
一方現在は以前であればPCで検索していたような、より多くの情報をスマホで検索するようになりました。そのため検索順位1位のページだけでは足りず、2位以降のページもクリックされるようになり、検索上位のページのクリック率の差が小さくなったわけです。
なおユーザーがスマートフォンを利用してより多くの情報を検索することになった背景には、以下のような背景があります。
- スマートフォンのデータ通信の高速化
- デバイスの巨大化
- モバイルファーストインデックス等による、スマートフォン向けサイトの質の向上
特にモバイルファーストインデックスやモバイルフレンドリーといったスマートフォン向けコンテンツにサイトが対応しているか否かという点は、検索順位の判定にも影響するほど大きな要素となりました。
モバイルファーストインデックスなどのスマホ向けの施策をまだ何も取り入れていないという場合は、スマートフォン向けのページを作成したり、コンテンツをスマートフォンでも見やすくするようにしたりするだけでもサイトの評価が上がる可能性があります。
モバイルファーストインデックスについては下記の記事で解説しています。
クリック率を上げる方法
ここまで検索順位別のクリック率について解説してきましたが、ここまでしてきたのはあくまで平均的な数値の話です。当然検索順位を上げることができれば、最も効果的にクリック率を上げることができますが、2位から1位に検索順位を上げるというのは簡単ではありません。そこで検索順位はそのままでも、少しでもクリック率を上げる方法を解説します。
ユーザーのニーズや意図を汲み取る
ユーザーはタイトルやスニペットを見て、そのページに自分が求める情報があるかどうかを判断して、クリックするかを決定します。そのためユーザーのニーズや意図を汲み取ってページのコンテンツの作成やタイトル付け、スニペットの編集を行うのが重要です。
たとえば「SEO クリック率 とは」で検索する方はクリック率とは何か知りたいだけでなく、実際にSEOを行なっており、クリック率を改善したいという意図を持っていると推測することができます。
そのため単にクリック率の定義を紹介するだけでなく、過去の検索順位別のクリック率やクリック率の改善方法を紹介することで、よりユーザーにとって魅力的なコンテンツの作成が可能です。そして内容に応じてタイトルやスニペットを設定しましょう。
先ほどのクリック率の例でいうと、クリック率の定義や過去のクリック率の情報はもちろんですが、クリック率をどうしたら改善できるのか、クリック率の高いページと低いページの違いなど、より内容が充実したページのほうがユーザーにとって有意義なため、ただクリック率の定義や用語解説をしただけのページよりもクリック率は高くなります。
ユーザーがサイトやコンテンツに何を求めているのか、どのような情報が欲しくて検索をかけているのか、といった点を考えてコンテンツを作成することで、よりクリック率の高いコンテンツを作成することが可能になります。ユーザーにとって検索しやすく、サイトのテーマや意図がユーザーに読み取りやすいようにしておくことが大切です。
検索意図については下記の記事で解説しています。
タイトルを見直す
ユーザーのニーズや意図を汲み取ってタイトルをつけるのは当然ですが、それ以外にもタイトルで拘るべき点は存在します。6W2H(WHO(誰が),WHOM(誰に),WHAT(何を),WHY(なぜ),WHERE(どこで),WHEN(いつ),HOW(どのように) HOW MUCH(どれくらい))の中でも特にWHAT,WHY,HOWを意識してタイトル付を行いましょう。
たとえば「保険 おすすめ」というキーワードでWHAT,WHY,HOWを意識してタイトルをつけると、「これだけ読めば安心(HOW)!将来の不安がなくなる(WHY)プロ目線のおすすめ保険(WHAT)」というようなタイトルをつけることができます。よりユーザーがクリックしたくなるようなタイトルを作成しましょう。
また、設定した検索キーワードをタイトルに含める、というのも代表的なテクニックの一つです。タイトルに設定した検索キーワードを含めることで、そのキーワードについて知りたいと思って検索をかけたユーザーにサイトを見てもらえる可能性が上がります。このように、検索で来てくれたユーザーにとって分かりやすいようにテーマを設定することで、よりクリック率の向上を見込むことができるようになります。
タイトルの付け方については下記の記事で解説しています。
meta descriptionを見直す
meta descriptionは検索結果のスニペットに表示されるWEBページの内容を説明する文章のことです。タイトルにはこだわってもmeta descriptionにはこだわらないというサイトは少なくありませんが、meta descriptionはタイトル同様にユーザーに見られています。
デフォルトだとページの冒頭部分が抜粋され、meta descriptionとして検索結果に表示されます。しかしそのままだとユーザーにページの内容が十分に伝わらないことが多いため、meta descriptionは手動で設定することをおすすめします。
meta description を設定する上で忘れてはいけないのが文字数です。meta descriptionを表示できるスペースは決まっているので、あまり長すぎると途中で切れて表示されないことがあります。スマホは50~70文字程度。PCは120文字程度であれば全文表示される範囲とされています。
この文字数内でサイトの概要やページの内容についての記述をする必要があるのですが、このときに検索キーワードを詰め込みすぎてしまうと、かえって見栄えが悪くなり、クリック率も伸びなくなってしまう、という悪影響を及ぼしてしまう恐れがあります。meta descriptionを設定する際は、文章が読みやすく設定されているか、ユーザーにとってサイトの内容がわかりやすく伝わる文章になっているか、といった点を必ずチェックするようにしましょう。
また、稀にサイト内のmeta descriptionを全て同じ文章で統一して設定しているサイトがありますが、ページごとの内容が伝わりにくくなってしまうのでおすすめしません。meta descriptionを設定する際は、面倒でも全てのページに違う文章を設定するのがおすすめです。
ディスクリプションについては下記の記事で解説しています。
ターゲット設定を明確にする
ターゲット設定を明確に設定することで、特定のユーザーにとってより強い訴求力を発揮することができます。例えば化粧品を取り扱っているサイトにターゲットを設定する場合、化粧品に興味のある女性を対象としたサイトを作るようにすることが重要です。化粧品に興味のない男性や、化粧品を使う必要のないユーザーに対して訴求を行っても、結果は出ませんしクリック率も上がりません。
サイトが何をユーザーに伝えたいのか、どのような層に商品を購買してほしいのかという点をあらかじめ明確にしておくことは、効率的なマーケティングを行うために非常に重要なポイントです。
具体的なデータや数字を入れる
具体的なデータや数字があるのであれば、そのデータや数字をどんどん入れて実績をアピールしていきましょう。
例えば、「業界で何位」「〇〇賞を受賞」という情報だけでは実績が具体的につかみにくい印象がありますが、「年間〇〇件のご依頼に対応」「年間○○社以上の運用実績あり」などの具体的な数字やデータがあると、ユーザーにとってよりわかりやすく、不安要素の解決にもつながります。
クリック率を上げるためには、実績をキャッチ―にアピールすることが必要です。特にmeta descriptionやタイトルなどの字数制限がある場合は、このようにデータや数字を入れておくだけで、ユーザーにとってわかりやすい指針となります。
まとめ
以前はスマホ版の検索順位別のクリック率は、1位のページに集中していましたが、スマートフォンを利用しての検索エンジンの利用がより一般的になった現在、スマホ版のクリック率は以前ほど1位に集中しなくなりました。検索順位が1位でなくても、タイトルやスニペット次第でクリック率を改善する余地が生まれたということです。
WHATやWHY、HOWを意識したタイトル付けや、内容をよりよく伝えるmeta descriptionの設定などを行なって少しでもクリック率を改善させましょう。
また、クリック率は一つの指針に過ぎないということも考慮しておきましょう。クリック率はユーザーからの一つの目安であり、いくらクリック率が高くとも商品が売れなかったり、サイトの内容をよく見てもらえず直帰率が高かったり、といったこともありえます。
サイトやコンテンツをユーザーによく見てもらうには、ユーザーがサイト内をよく見て回りたくなるようなしっかりとした情報量のあるページを作成する、ということが一番大切です。クリック率の向上と同時に、ユーザーにとって有益なページを作成するように心がけるようにしましょう。
関連