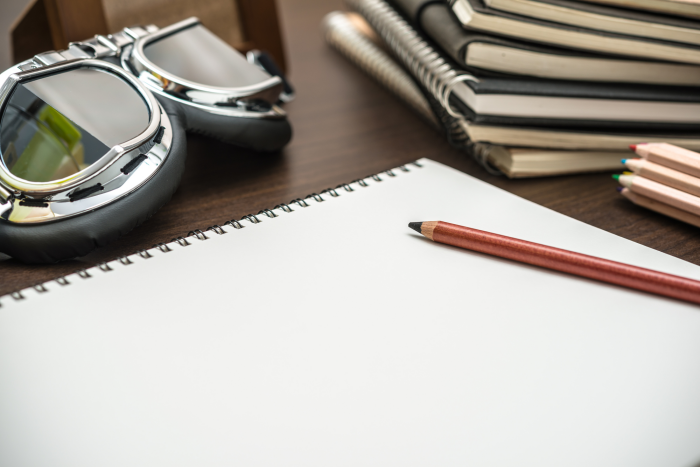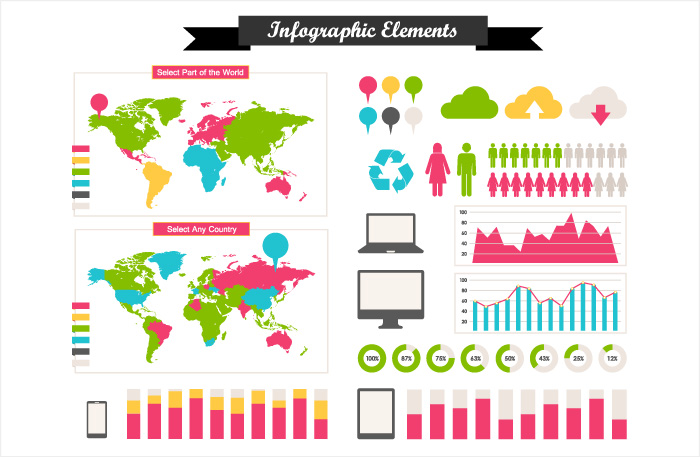サブドメインとサブディレクトリの違いとは?新サイトのSEOは別ドメインの方が有利?
2020.02.28
Web用語には紛らわしい用語が数多くありますが、「サブドメイン」と「サブディレクトリ」もその一つ。そこで今回は、サブドメインとサブディレクトリの違いを明確にし、SEO効果の優劣やメインドメインに与える影響、さらに新規サイトでは別ドメインとサブドメインのどちらを使うべきなのかなど、詳しくまとめてみました。
サブドメインとは? そもそもサブドメインとは何なのでしょうか。URLはインターネット上の住所のことで、その一部がドメインです。 ペコプラのSEO対策実例・コラムページのURLは「https://pecopla.net/seo-column/」です。このURLの「pecopla.net」の部分がドメインにあたります。
そして、サブドメインは「pecopla.net」というメインドメインを分割したものを指し「https://sub.pecopla.net/」といったURLになります。「pecopla.net」というドメインの中に、「sub」というサブドメインで区切られた部分があるとイメージすればわかりやすいでしょう。
例えば「https://net-shop.net/」というECサイトを運営している場合、サブドメインでカテゴリ別にURLを増やすとすると、本を販売する「https://book.net-shop.net/」、おもちゃを販売する「https://toy.net-shop.net/」とサイトを分けることができます。サブドメインはメインドメインを区分けする際の名前なので、自由に設定することが可能です。
下記ページでドメインやドメインの選び方について詳しく説明しているので、併せて参照してみてください。
サブドメインとサブディレクトリの違いは? サブドメインとの使い分けに悩みがちなのが「サブディレクトリ」です。ペコプラのコラムページのURLは「https://pecopla.net/column/」となっており、「column」というディレクトリが設定されていて、その中にコラムコンテンツが入っている状態です。
下記のようにURLを比較してみると違いが明確になります。
サブドメイン:https://sub.pecopla.net/
サブディレクトリ:https://pecopla.net/sub/
イメージとしては、メインドメインが「本家」、サブドメインが「分家」、サブディレクトリが「本家の一部屋」です。
本家と分家はしっかりとしたつながりがありますが、あくまでも別の家です。メインドメインとサブドメインもそのような関係性で、サブドメインはクローラーに新しいひとつのドメインだと見なされます。サブドメイン同士はお隣さんといったイメージです。
一方、サブディレクトリはメインドメインの中にあるひとつの部屋にあたります。複数のサブディレクトリを設定している場合は、メインドメインという家の中にある部屋同士になります。メインドメインの下層に作られるのがサブディレクトリで、サブドメインの下層にサブディレクトリを作ることもあります。
また、サブディレクトリの下にさらにディレクトリを作成し、「https://pecopla.net/sub/directory/」のように階層を深めることもあるでしょう。その場合は、「sub」も「directory」もサブディレクトリと呼びます。
サブドメインのSEO効果は? この段落では、サブドメインのSEO効果について4つの項目に分けて解説します。
SEOにおけるサブドメインのメリット 結論から言うと、サブドメインを利用するSEOのメリットらしいメリットは特にありません。強いて言えば、メインドメインとは違った内容のコンテンツを、新たなサイトとして運営できる点が挙げられます。
メインドメインで構築しているサイト内で分野の違うコンテンツを展開してしまうと、サイトの一貫性が失われ、検索エンジンに専門性の薄いサイトだと見なされてしまうかもしれません。そのような場合にメインドメインと分野の異なるコンテンツを分離できるのがサブドメインのメリットだと言えるでしょう。
言い換えれば、メインドメインとは別サイトとして運営することで、サブドメインの専門性の高さをメインドメインとは別にアピールできるということでもあります。つまり、分野の異なるコンテンツを分離してそれぞれの専門性を損なわせないことで、メインドメインの順位が下がるのを防ぎつつ、さらにサブドメインで構築した新サイトも上位表示の可能性を高められるのです。
SEOにおけるサブドメインのデメリット 対してデメリットは、サブドメインの評価が良くも悪くもメインドメインの評価によって影響を受けやすいという点でしょう。
確かに、サブドメインはメインドメインからの評価を受け継ぐため、全くゼロの状態から評価されるわけではありません。そのため、新しくドメインを取得した新規サイトよりもインデックスされやすい傾向にあります。
その反面、Googleからペナルティを受けるなどメインドメインの評価が低い場合はサブドメインの評価もマイナスからスタートするため、新規ドメインよりも不利になってしまうのです。
新規ドメイン(別ドメイン)については下記の記事でも解説しています。
Googleが忠告するサブドメインのSEO手法 サブドメインやサブディレクトリに関して、Googleが2019年8月15日に下記のようなツイートをしています。
「サブドメインに第三者がコンテンツを公開して良いか」という質問に対し、Googleは「その行為自体はガイドラインに違反していない」と回答しています。
そのうえで、第三者にサブドメインを提供してコンテンツを作成してもらうことで検索結果からの流入を増やそうとするSEO手法に対し、システムの改善が進んでいるとコメントしているのです。
前述の通り、サブドメインは新たなドメイン(Webサイト)としてGoogleに認識される反面、SEOの評価に関してはメインドメインとの関係性が強く維持されています。つまり、サブドメインへの検索流入を増やすことで、サブドメイン及びメインドメインの評価を上げようとすることができるということです。
ただし、Googleは上記ツイートを通してこういった手法を推奨しないと明確に宣言しています。 そのため、ツイート時点では明確な不正とは定義されていないものの、Googleに好まれるSEO手法とは言えません。
事実、「国や都市ごとにサブドメインを作る方法はSEOにとって有効か?」という質問に対し、Googleのジョン・ミューラー(John Mueller)氏はSEO系のフォーラム で下記のように回答しています。
サブドメインは1つのサイトの一部なので、検索順位にとって優位にはならない
誘導ページの量産と同じ行為に相当するため、むしろスパムチームの監視対象になる
今後はガイドラインが変更になる可能性もあるので、メインドメインの一部に見せ掛けるためのサブドメイン、サブディレクトリの第三者への提供は避けておく方が無難でしょう。
検索結果に表示される数が制限されている 一昔前は、メインドメイン(ルートドメイン)と関連性の高いサブメインを大量に作ることで、同一キーワードでの上位表示を独占するSEO手法が横行していました。
しかし、現在ではドメインの種類ごとに下記のようなルールが設けられており、検索結果に表示されるコンテンツ数が制限されているようです。
▼Yahoo!JAPAN
サブドメイン:2つ
別ドメイン:2つ
同一ドメインの別ページ:2つ
▼Google
サブドメインを含めた関連ドメイン:例外もあるが通常3つ以上は表示されにくい
同一ドメインの別ページ:2つ目以上は表示されにくい
下位ではルールが弱まる:800位以後に同ドメインが20ページ表示されたこともある
特にGoogleでは、より多くのユーザーを満足させるために内容の異なるコンテンツをバランス良く上位に表示させる仕組みを採用しているとアナウンスしています。
つまり、サブドメイン内コンテンツの内容がメインドメイン内コンテンツの内容と類似している場合、両方が上位に表示される確率は極めて低いのです。
類似コンテンツ(重複コンテンツ)については下記の記事でも解説しています。
サブドメインとサブディレクトリのSEOに優劣はない 2020年1月10日、Googleのトレンドアナリストとして知られるジョン・ミューラー(John Mueller)氏はGoogle Webmaster Hangoutに参加し、SEOにおけるサブドメインとサブディレクトリの優劣について言及しています。
ここでは、Googleの動画から注目すべきコメントをピックアップしてみました。
サブドメインとサブディレクトリのSEO効果は基本的に同等
どちらを選ぶか迷っているなら、Web運営者が使いやすい方を選べば良い
つまり、サブドメインとサブディレクトリのどちらにすべきかを判断するポイントは、「SEOのため」ではなく「目的に沿った使いやすさ」なのです。
VIDEO
サブドメインの管理メリット サブドメインには、管理上のメリットがいくつかあります。
管理コストの削減 サブドメインは、メインドメインを取得していれば作成することができるので追加費用が掛かりません。新たなサイトを構築する際に、その都度新たなドメインを取得していては、その分手間とコストが掛かります。希望するドメインが新たに取得できないこともあるかもしれません。
複数のサブドメインでサイトを運用する場合も、URLのメインドメイン部分は共通なので、メインドメインとサブドメインの運営者が同じだとすぐにわかるのもメリットだといえるでしょう。追加費用なしでドメインを使い分けられるメリットは、管理コストの削減につながります。
ただし、サブドメインの追加可能数や設定方法などはサーバーによって異なります。基本的にサブドメインの追加に費用は掛かりませんが、サーバーによってはオプション料金などが必要となる場合があります。事前に契約サーバー会社によく確認しましょう。
独立したアクセス解析が可能 サブドメインはメインドメインとは異なる新しいドメインとして認識されます。独立したサイトとしてサブドメインごとにアクセス解析できるので、サブドメイン単体での問題点に気付きやすいというメリットがあります。
広い範囲だと見落としがちな課題点も、サブドメインという範囲を絞った枠組みの中なら見つけやすいこともあるでしょう。即座に課題点を改善していくことで、よりユーザーにとって有用な記事となりSEO効果も見込めるかもしれません。
また、Search Consoleはサブドメインごとに設定を行う必要があります。
独立したサイト設計 サブドメインの最大のメリットは、メインドメインと切り離して独立したサイト設計を行えることです。例えばメインドメインで運営するコーポレートサイトがあり、新たにオウンドメディアを運営する場合など、コンテンツ内容がどうしてもコーポレートサイトの枠組みから外れてしまうことがあるでしょう。
そういった場合、独立したサイトとみなされるサブドメインであれば、新たなオウンドメディアの特化性だけを評価してもらえます。メインドメインにさまざまな情報が混在して専門性を損なうといった事態も避けることができます。
逆に、メインドメインと関連性の高いコンテンツを作成する場合は、サブドメインでなく、メインドメインから独立させないサブディレクトリでの運営の方が適しているでしょう。
サブドメインとサブディレクトリの使い分け サブドメインとサブディレクトリのどちらを使おうとSEOに優劣はありませんが、決定的に違うのが「担っている役割」です。まずは、それぞれの役割について理解しておきましょう。
▼役割の違い
サブドメイン:同一ブランドで異なるテーマを扱う
サブディレクトリ:メインドメインとまとめられる類似テーマを扱う
単純にどちらを選べばいいというわけではなく、上記の役割を踏まえたうえで目的やコンテンツの内容に合わせて使い分ける必要があります。
▼サブドメインにすべきケース
メインドメインとの関連性が薄い場合
メインドメインのECサイトに、追加でオウンドメディアを立ち上げたい場合
前述の通り、サブドメインは新しいひとつのドメインだと見なされます。そのため、メインドメインの内容とは違うコンテンツを作成する場合は、サブドメインの方が向いているのです。
▼サブディレクトリにすべきケース
メインドメインとの関連性が強い場合
「iPhone」「iPad」のようにジャンルは異なるが基本のテーマが同じ場合
サブディレクトリはメインドメインの一部です。そのため、サイト内に全く関係のないコンテンツが混ざってしまうと、SEO評価が下がってしまう可能性があります。
サブドメインがメインドメインに与える影響 サブドメインの特徴が分かったところで、メインドメインに与える影響について見てみましょう。
サブドメインはメインドメインの外部リンクではない 「サブドメインを増やせばメインドメインへの被リンクが増えるのでは?」と思われがちですが、そうとは限りません。
なぜなら、Google では「サブドメイン=メインドメインの内部リンク」と認識しているからです。
実際、メインドメインの外部リンクをGoogle Search Consoleで確認してみると、サブドメインは一覧表示に含まれていないと分かるはずです。
外部リンクについては下記の記事で解説しています。
サブドメインの被リンクが多いほどメインドメインに有利 とはいえ、サブドメインによるメインドメインへのメリットが全くない訳ではありません。
サブドメインはメインドメインの内部リンクとして扱われるため、サブドメインが獲得している被リンクが多いほどメインドメインへの被リンクも増えると解釈できるのです。
「多くの被リンクを獲得しているWebページがメインドメイン内部にある状態」と言った方がイメージしやすいかもしれません。
つまり、サブドメイン自体はメインドメインの外部リンクではないが、サブドメインの被リンクはメインドメインのSEOにとって有利に作用するのです。
まとめ SEO効果において、サブドメインでのサイト運営は大きなメリットもデメリットもありません。しかし、メインドメインの専門性に影響を及ぼすような、メインドメインと関連性の薄いサイトを構築する場合には大きなメリットがあるといえるでしょう。運営するサイトの内容によって、うまくサブドメインを使い分けましょう。
関連