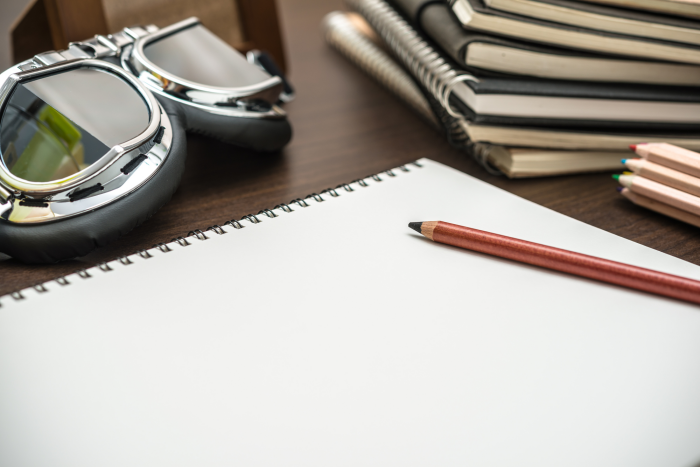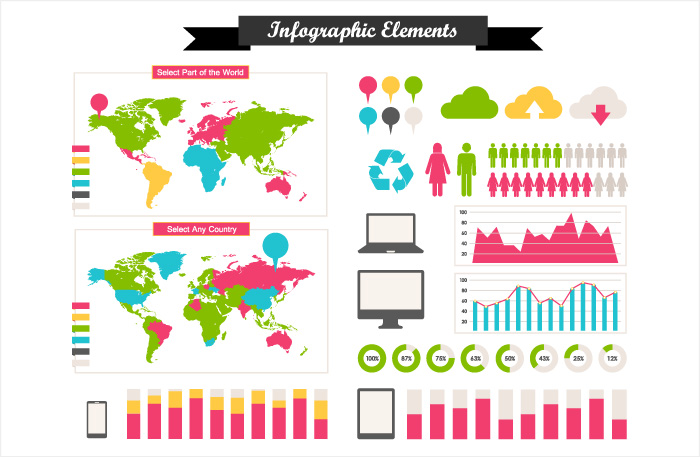Googleが推奨するnofollowの正しい使い方とは?
2023.08.10
外部リンクを設定する際の注意点はいくつかありますが、「nofollow」もその1つ。
なかには、nofollowを必要ないリンクに設定してしまい、本来のSEO評価が目減りしているケースもあるようです。
そこで今回は、nofollowの効果・SponsoredやUgcとの違い・使うべきケース・設定方法・よくある質問について解説していきます。
nofollow属性とは?
nofollowとは、自サイトと外部リンク先との関係性を示すrel属性値の一種で、外部リンクに設定することでクローラーに対して「無関係のサイトなので辿らないでね」と伝えることができます。
詳しくは後述しますが、Googleはnofollowを使うべきケースとして下記の2つを挙げています。
- 自サイトとリンク先を関連付けたくない(推奨したくない)
- リンク先をクロールさせたくない(ページの評価をリンク先に渡したくない)
Webサイトを運営していると、やむを得ず信憑性に欠けるページや低評価のページに外部リンクを設定することがありますが、nofollowを使えば「リンクは貼っているけど、推奨サイトじゃないよ!」という立場をアピールできるのです。
ただし、nofollowを設定したからと言って、リンク先へのクロールを100%ブロックすることはできません。
nofollow属性が初めて導入された2005年当初は「リンク先を辿るな!」という「命令」でしたが、2019年9月以降はリンク先へのクロールを控えるように促す「ヒント」または「要望」という扱いに変更されました。
なお、nofollowの使用対象はあくまで「外部リンク」のみに限定されていますので、Googleが公式サイトに明記している通り、内部リンクにはrobots.txtの「disallow」を使用しましょう。
nofollow属性の効果とは?
外部リンクにnofollowを設定する前の通常リンクと、設定後の違いを比較してみましょう。
両者を比較することで、nofollow属性の効果が一目で分かります。
|
nofollow設定前 |
nofollow設定後 |
| ステップ1 |
クローラーが「このリンク先はリンク元と関連性がある!」と認識する |
クローラーに「このリンク先はリンク元と無関係!」と伝わる |
| ステップ2 |
クローラーが自ページから外部リンク先へ辿り着く(クロールされる) |
自ページから外部リンク先へのクロールされにくくなる |
| ステップ3 |
リンク元ページの評価(ページランク)が、リンク先に渡ってしまう |
リンク元ページの評価(ページランク)が、リンク先に渡り難くなる |
| ステップ4 |
リンク元の評価が影響し、品質の低いリンク先のSEO評価が不当にアップすることもある |
リンク元の評価によって、品質の低いリンク先のSEO評価が不当にアップするリスクが減る |
事実、Googleの Gary Illyes(ゲイリー・イリース)氏は、「悪質なサイトを助ける必要はないから、nofollow を使用して下さい!」といった主旨のツイートを投稿しています。
nofollowの使い方は変化している!
この章では、Googleがnofollowを導入した背景や使い方の変化、新たに導入された類似タグについて、時系列でまとめてみました。
| nofollow導入前 |
・リンク元のSEO効果を得ようする、「自作自演の不正行為」が蔓延 |
| 2005年1月18日 |
・コメントスパム対策として「nofollow」が導入される |
| nofollow導入後 |
・SNSや口コミサイトなどに投稿したコメントに自サイトへのリンクを貼る、自作自演行為が激減
・「すべての外部リンクにnofollowを設定すべき」という間違った考え方が広まり、有益な外部リンクも辿れなくなってしまった |
| 2019年9月10日 |
・nofollowの役割が、リンク先へのクロールをブロックする「命令」から、「ヒント/要望」に変更され、リンク先を辿るかどうかは、検索エンジンが判断するようになる
・有料リンク専用のrel属性値、「sponsored」を導入
・ユーザー生成コンテンツ専用のrel属性値、「ugc」を導入 |
新たに導入されたrel属性値
Googleは、nofollowの影響が「命令」から「ヒント/要望」に変わったと公式サイトで発表した際、同時に下記2つの新しいrel属性値を追加したこともアナウンスしています。
nofollow、Sponsored、Ugcには、「リンク元とリンク先の関係性を表している」「扱いはヒント」「ページランクを渡さない」という3つの共通点があります。
sponsoredとは、Googleが「有料リンク専用」として推奨しているrel属性値です。
- 対象:バナー広告、アフィリエイトリンクなど
- 表している関係性:報酬が発生する関係
たとえば、広告リンクに関係性を示すrel属性値が付加されていなかった場合、「広告リンクを増やす=より多くリンク元の評価が得られて検索ランキングで有利になる!」、といった間違った考え方が成り立ってしまいます。
だからこそGoogleは、検索ランキングが不正に操作されるのを防ぐために、広告リンクと通常リンクを区別するようガイドラインで提示しているのです。
ugc
ugcとは、Googleが「ユーザー作成型コンテンツ専用」として推奨しているrel属性値です。
- 対象:コメントの書き込み、フォーラムの投稿など
- 表している関係性:売り込む必要がない関係
3種類とも外部リンクとの関係性をクローラーに伝えるために使用するrel属性値ですが、設定する際はGoogleが推奨している下記の使い分けに従いましょう。
| 広告などの有料リンク |
rel=”sponsored” |
| コメント投稿などユーザーが作成したリンク |
rel=”ugc” |
| 上記2つに該当せず、なおかつ下記2つどちらかに当てはまる場合
・自サイトとリンク先を関連付けたくない(推奨したくない)
・リンク先をクロールさせたくない(ページの評価をリンク先に渡したくない) |
rel=”nofollow” |
Google推奨!nofollowが必要なケースは2つ
まずは、Googleの公式見解を見てみましょう。

引用:Google検索セントラル(Google に外部リンクの関係性を伝える)
つまり、Googleが推奨している「nofollow」を使うべきケースとは、有料リンク(sponsored)にもユーザー作成型コンテンツ(ugc)にも該当せず、なおかつ下記のどちらかに該当する場合に限定されているのです。
- 自サイトと関連付けたくない
- SEO評価が渡らないようクロールを防ぎたい
自サイトと関連付けたくない
Googleは、自サイトと関連付けたくない、つまり推奨していると誤解されたくない場合は、外部リンクにnofollowを設定すべきだと推奨しています。
たとえば、下記のケースに当てはまる場合は、nofollowを付加して自サイトの立場をクローラーに伝えましょう。
- NG例として、低品質ページに外部リンクを貼っている
- 余談として、コンテンツの主旨と関連性が薄いページに外部リンクを貼っている
SEO評価が渡らないようクロールを防ぎたい
Googleは、リンク元からリンク先へクロールさせたくない場合も、nofollowを使うべきケースとして推奨しています。
その目的は、リンク先がクロールされた時に自サイトのランキング評価がリンク先に渡るのを防ぐため。
Webサイト内にrel属性値が設定されていない外部リンクがあると、無条件でクロールされて自サイトのSEO評価がリンク先に渡ってしまう可能性があるのです。
nofollow設定の記述例
ここからは、nofollowを設定する2つの方法をご紹介します。
- 特定のリンクに設定する方法
- ページ全体に設定する方法
特定のリンクに設定する方法
特定の外部リンクだけにnofollowを設定する場合は、「aタグ内」に記述します。
<a rel="nofollow" href="辿って欲しくないURL/">アンカーテキスト</a>
ページ全体に設定する方法
一方、ページ全体にnofollowを設定する場合は、「metaタグ内」に記述します。
<meta name=”robots” content=”nofollow“>
nofollow関連のよくある質問
最後に、nofollowに関するよくある質問をご紹介します。
- nofollowにSEO効果はあるの?
- disalloとの違いは?
- noindexとの違いとは?
- dofollowとの違いは?
- noopener やnoreferrerとの違いは?
nofollowにSEO効果はある?
たしかにnofollowは自作自演のリンクでSEO評価を得ようとしている人の不正行為を予防する効果は期待できますが、自サイトにおけるSEO対策の一環ではありません。
つまり、「すべての外部リンクにnofollowを設定するとSEO評価がアップする!」という説は、間違いなのです。
事実、Googleのジョン・ミュラー(John Mueller)氏は、2019年7月30日付けのSearch Engine Journalで、同様の見解を述べています。
disalloとの違いは?
どちらも、検索エンジンに対し「このリンクを辿る必要はないよ!」と意思表示をし、クロールを抑制するために使用しますが、対象が異なります。
- nofollow:外部リンクが対象
- disallo:内部インクが対象
たとえば、サイト内のページ数が多すぎてサーバーに負荷がかかっている場合は、重要度の低いページへの内部リンクにdisalloを設定することで、問題が緩和されます。
noindexとの違いとは?
nofollowは、外部のリンク先が「クロール」されるのを防ぐために使用します。
これに対し、自サイトのコンテンツが検索結果に表示されないよう、「インデックス」をブロックしたい時に使うのがnoindexです。
なお、noindexにクロールを防ぐ効果はありません。
dofollowとの違いは?
「nofollow」はページ評価をリンク先に渡るのを防ぐために使用するのに対し、ページ評価がリンク先に渡るのが「dofollow」の特徴です。
一般的に、dofollowは外部リンクを設定すると自動的に付加されます。
noopenerやnoreferrerとの違いは?
ざっくりと言うと、noopener やnoreferrerはtarget=”_blank”を使って「新しいタブ」でリンク先を表示させる際、セキュリティを強化するために使用する属性値を指しています。
target=”_blank”にnoopenerを付けずにリンク先を表示すると、新しいタブで開いたページから元タブのページを操作されてしまう可能性があるのです。
また、target=”_blank”にnoreferrerを付けておけば、IDなどの重要な情報がリンク先に渡ってしまうリスクを回避することができます。
nofollowにはページ評価をリンク先に渡るのを抑制する効果があるため混同されがちですが、noopenerやnoreferrerとはリスクの種類が違うことを覚えておきましょう。
まとめ
インターネット上では、「内部・外部を問わず全てのリンクにはnofollowが必須!」という意見を目にしますが、これは間違った情報です。
Googleが公式サイトで推奨している通り、nofollowを使用すべきなのは「自サイトと関連付けたくない場合」もしくは「SEO評価が渡らないようクロールを防ぎたい場合」、この2つに限定されています。
また、有料リンクにはsponsoredを、ユーザー作成型コンテンツにはugcを設定するなど、適切に使い分けることが重要です。
関連